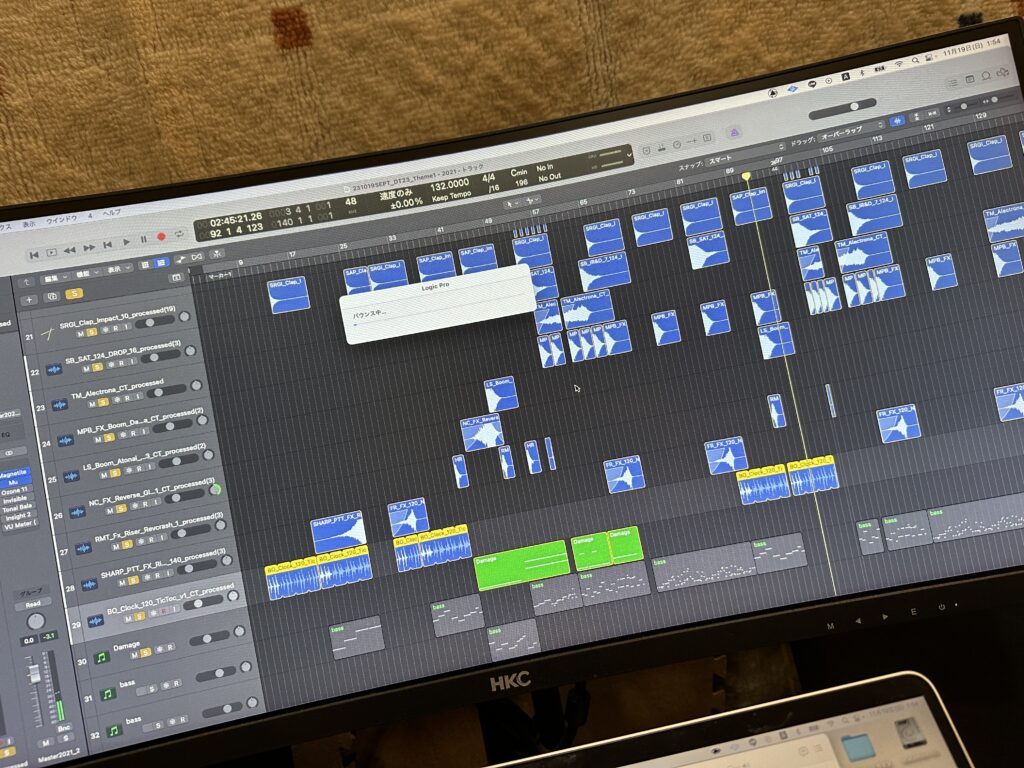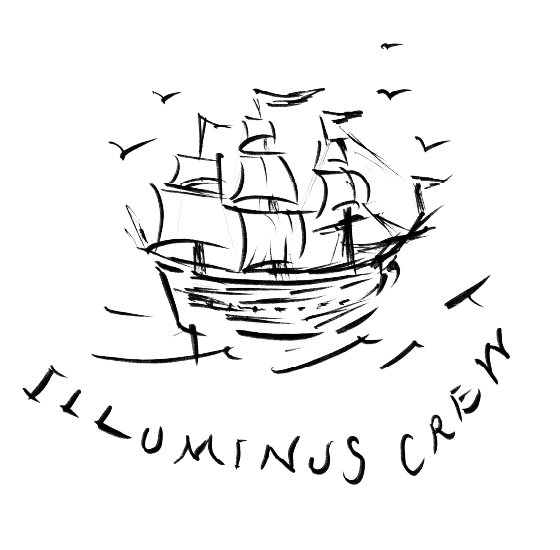音が紡ぐ女王ステと王ステの歴史
に関するその他の体験
-

26.2.13 思いだす
舞台『虚の王:‖』感想ポストまとめ
舞台「虚の王:‖」を観劇いただいた方の感想まとめ
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
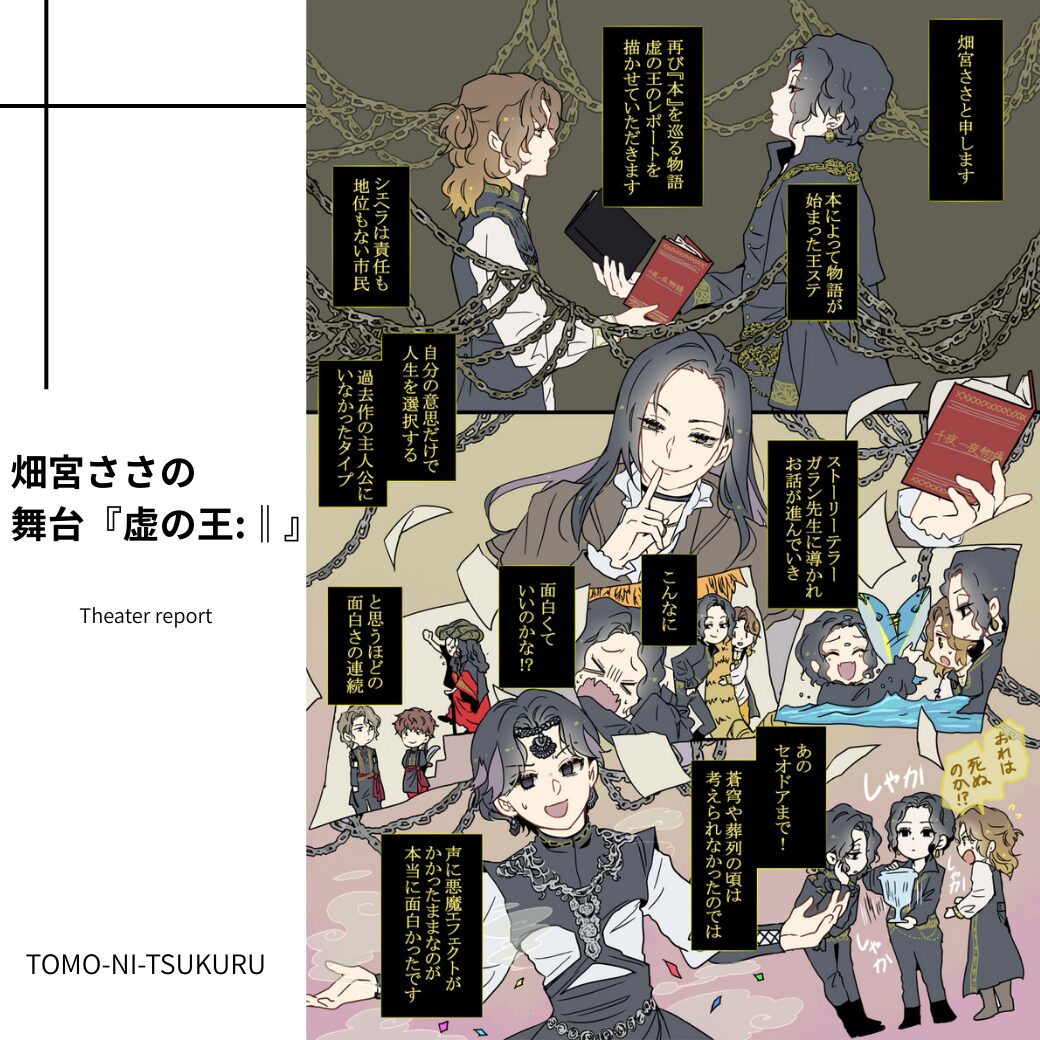
26.2.6
畑宮ささの舞台「虚の王:‖」参列レポート
彼の生を見届けた者としてーー観客が語る『虚の王:‖』
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

26.1.30 思いだす
女王輪舞配信中!ジャックシリーズ徹底解説!
「女王ステ」ジャックシリーズを徹底解説いたします!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

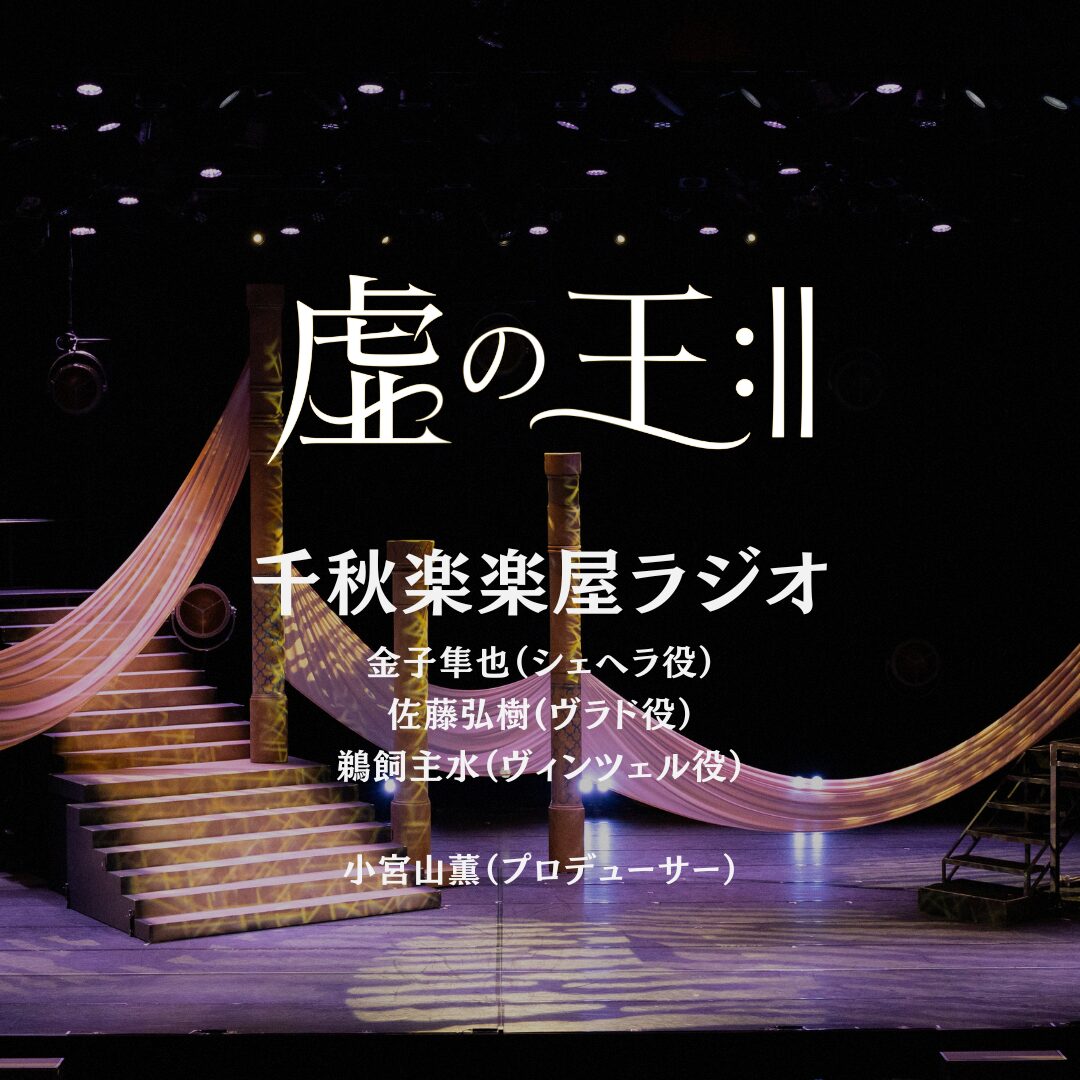
26.1.19
舞台「虚の王:‖」千秋楽 楽屋ラジオ
千秋楽直後の想いが詰まったラジオです!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
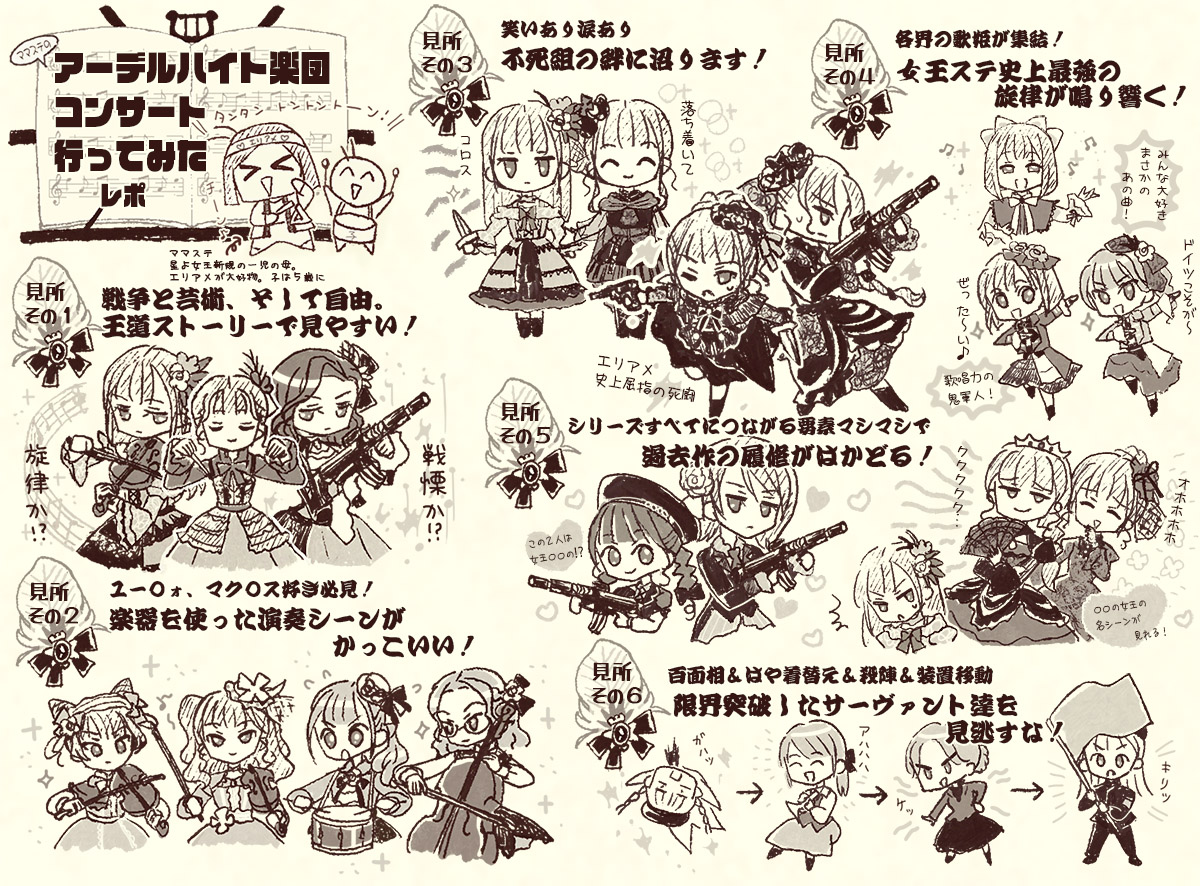
25.11.27 思いだす
ママステの「女王旋律」観劇レポート
アーデルハイト楽団コンサート行ってみた!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

25.11.26 思いだす
「女王旋律」感想ポストまとめ
「女王旋律」を観劇いただいた方の感想まとめ
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

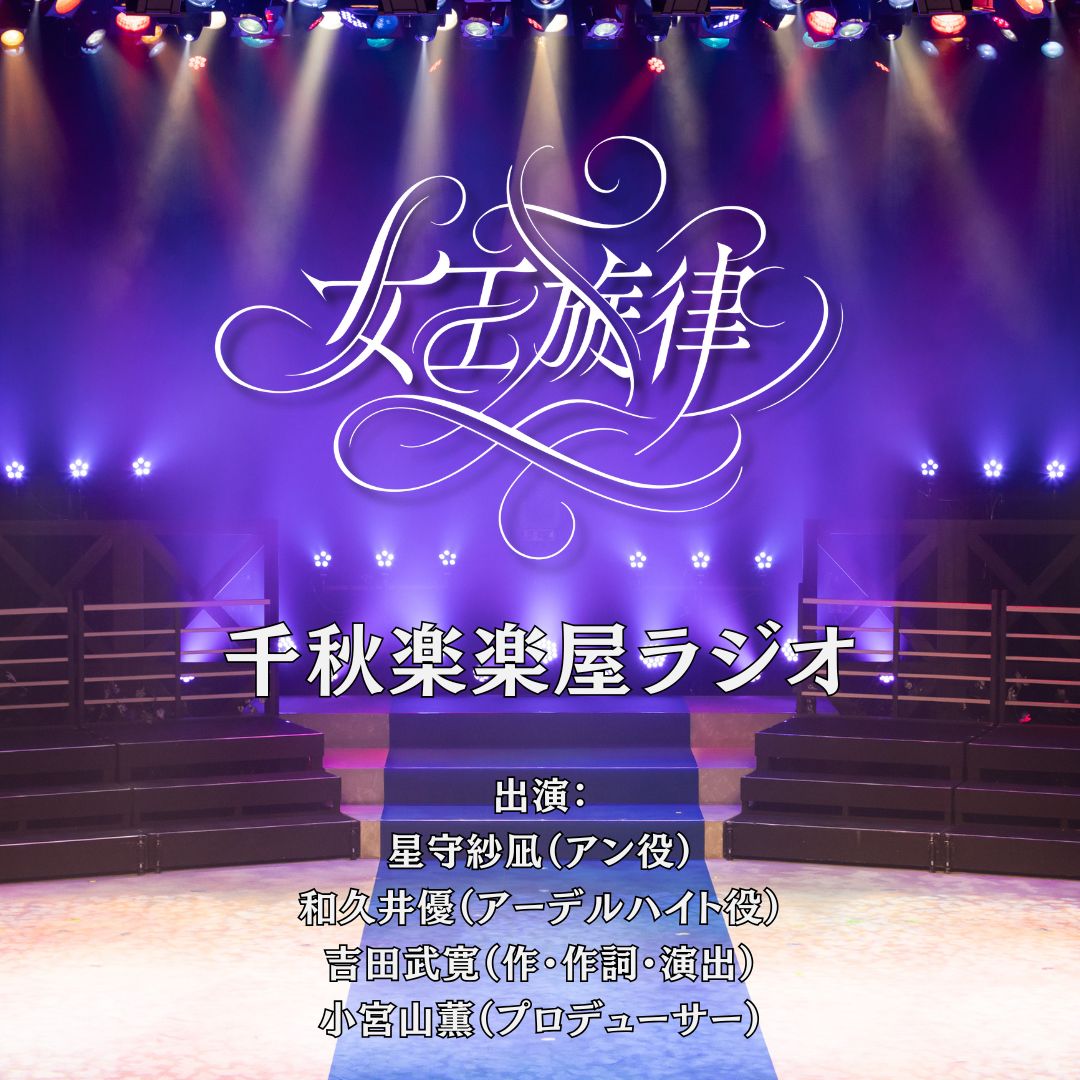
25.11.19 語りあう
「女王旋律」千秋楽 楽屋ラジオ
星守紗凪、和久井優の役に込めた思いを語る
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

25.10.28 思いだす
『王ステ』FAN ART COLLECTIO...
『王ステ』シリーズ5周年を記念したFA特集!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

25.10.23 思いだす
シリーズを支えたキャスト&クリエイター陣が語...
『王ステ』5周年記念──キャスト&クリエイターからメッセージが到着!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

25.10.13 思いだす
劇場以外でも楽しめる“王ステ体験”まとめ!
『王ステ』5周年記念──シリーズをもっと楽しむための完全ガイド!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-


25.9.26 待ちのぞむ
「女王ステ」アンの変遷を追って──
アンを演じ続けてきた星守紗凪ロングインタビュー
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
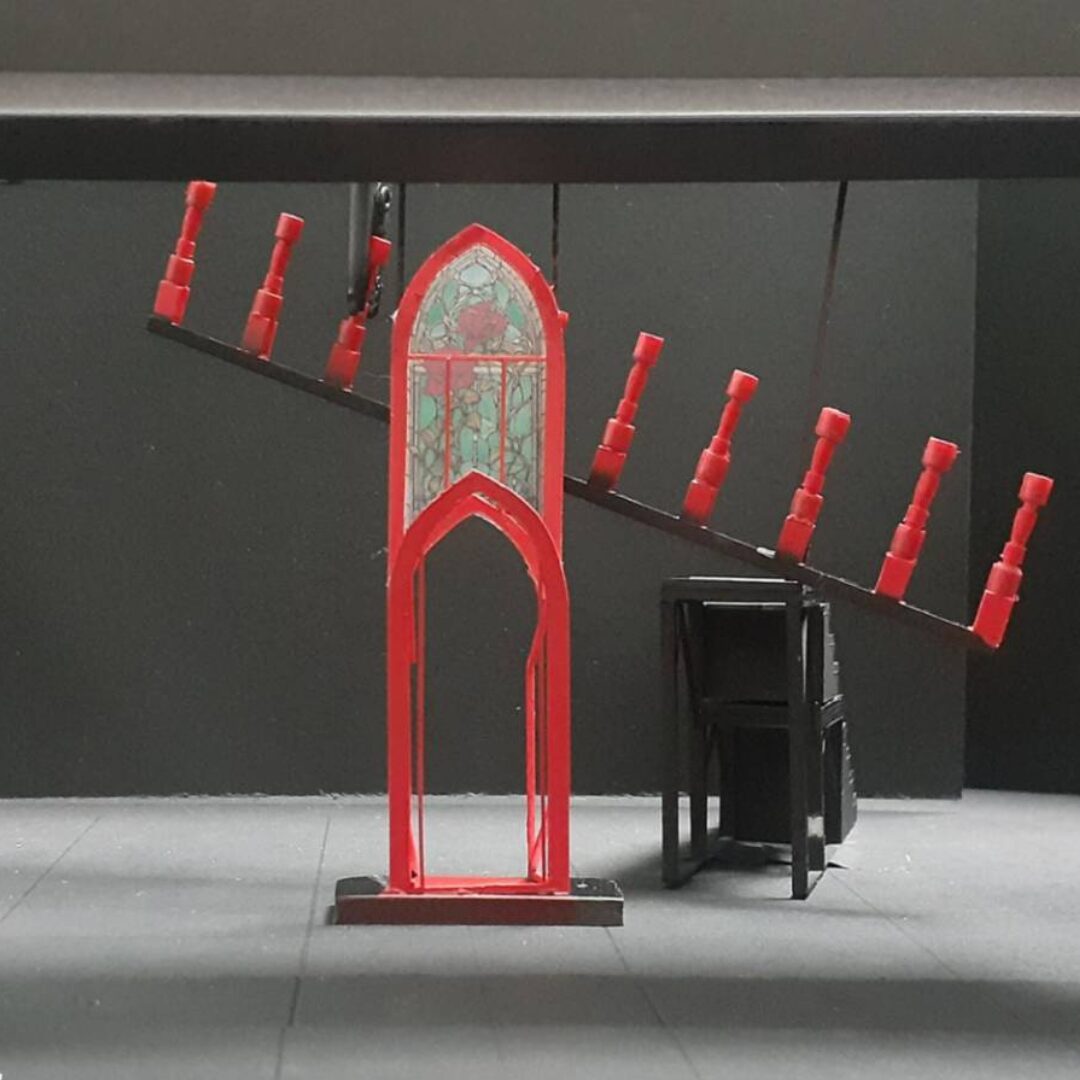
25.8.12 思いだす
舞台「葬列の王」美術スケッチ公開
「葬列の王」の世界をかたちづくる、舞台美術を公開!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

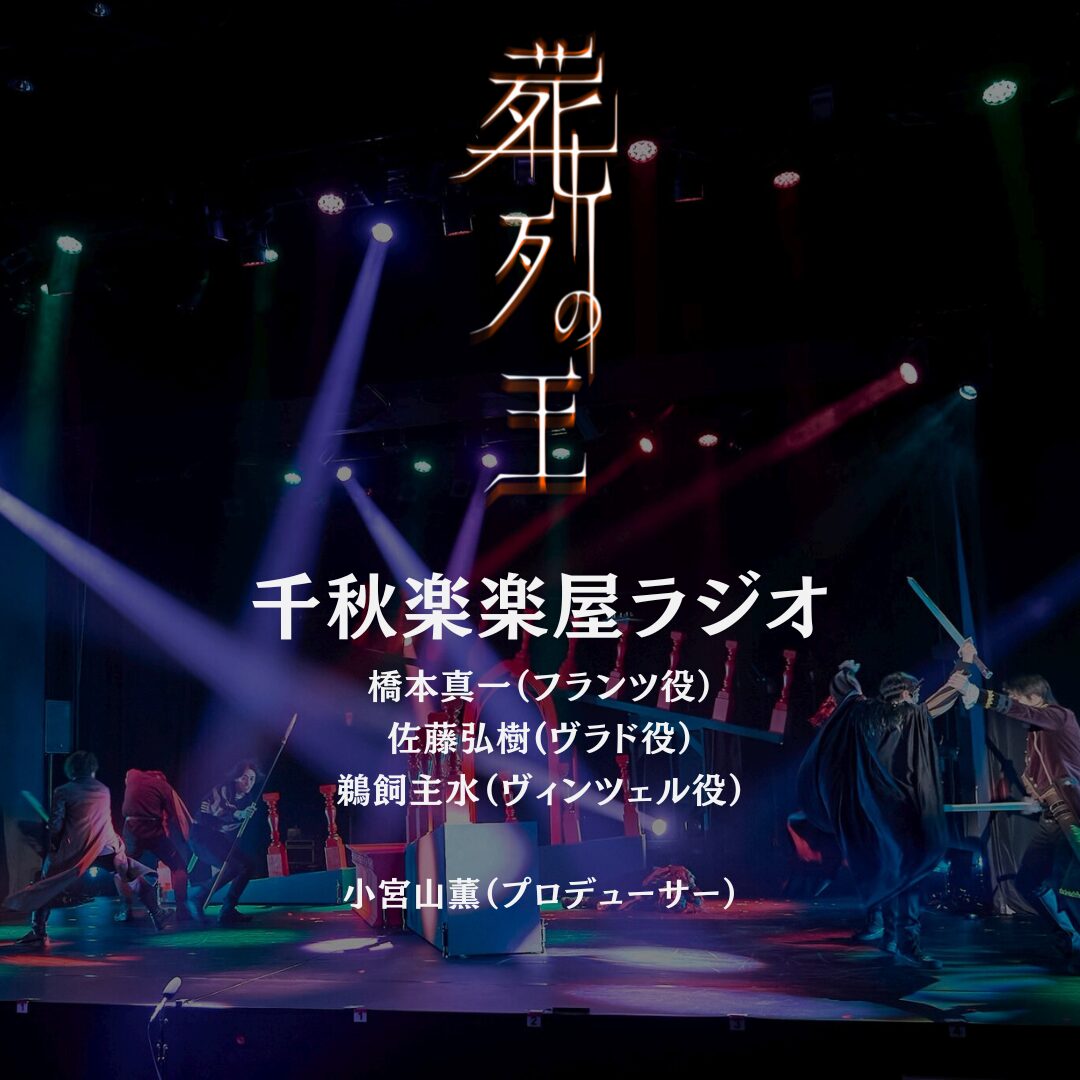
25.8.12 思いだす
王ステ『葬列の王』楽屋トークをお届け
『葬列の王』 千秋楽ラジオを特別公開!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

25.8.10 ともに創る
舞台「葬列の王」FA
この愛こそが芸術だ!「葬列の王」ファンアートをご紹介!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
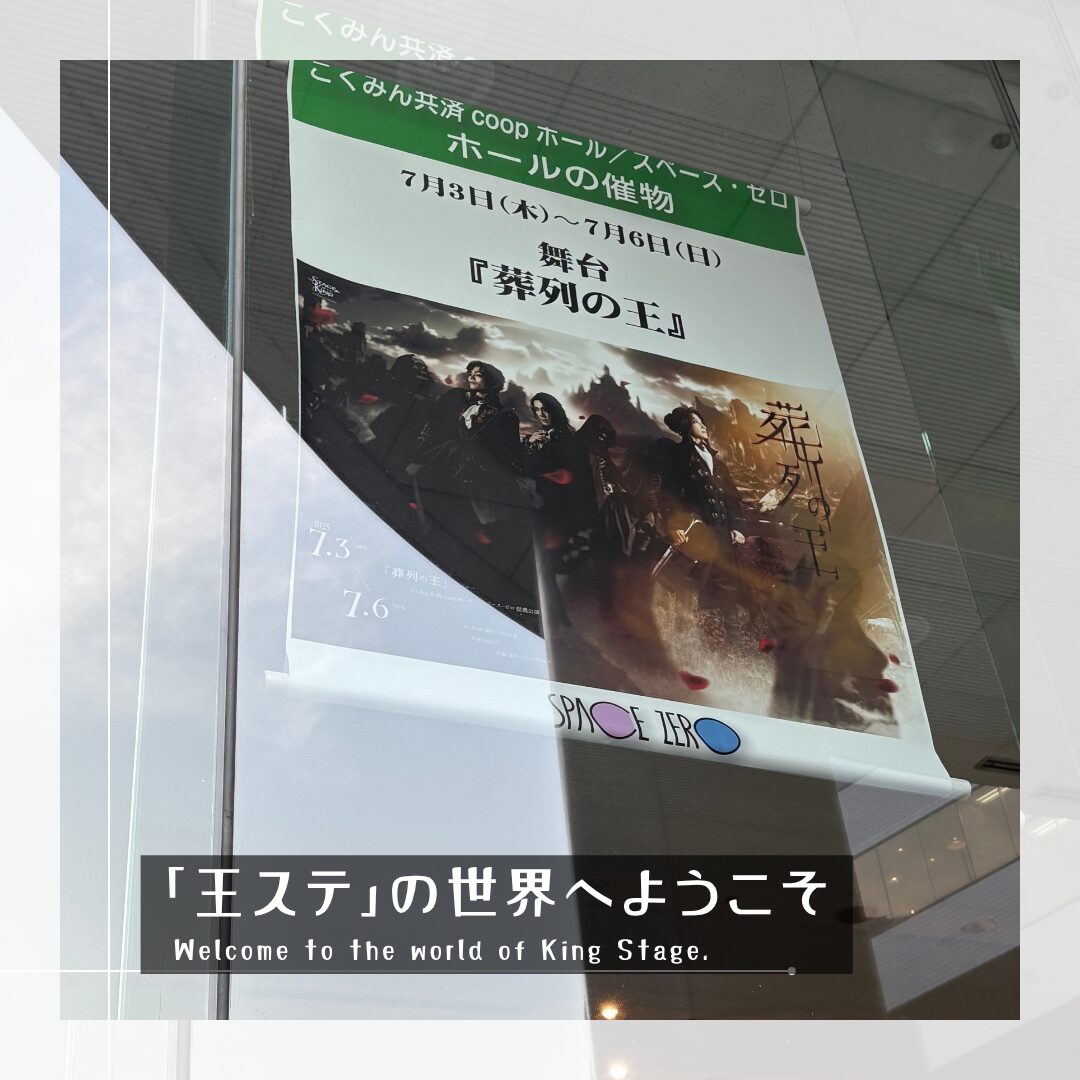
25.8.8 思いだす
「王ステ」の世界へようこそ
舞台「葬列の王」初観劇感想まとめ
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
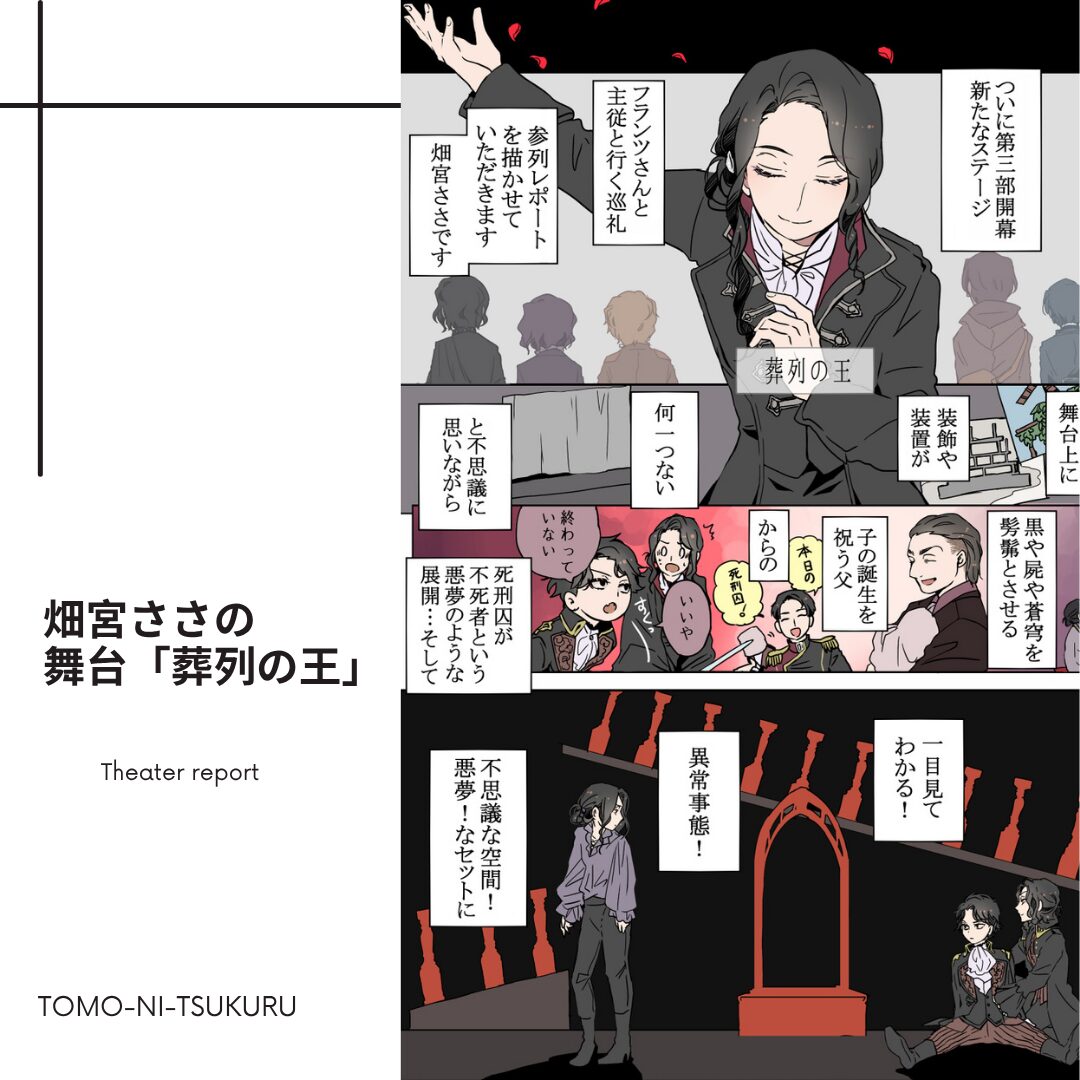
25.8.5 ともに創る
畑宮ささの舞台「葬列の王」参列レポート
彼の生を見届けた者としてーー観客が語る『葬列の王』
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-


25.6.16 語りあう
『王たちの流儀』Vol.4:輝山立
『王たちの流儀』Vol.4:輝山立
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-


25.6.8 語りあう
『王たちの流儀』Vol.3:磯野大
王ステシリーズの俳優に迫るSKETCH新連載企画 Vol.3-1
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
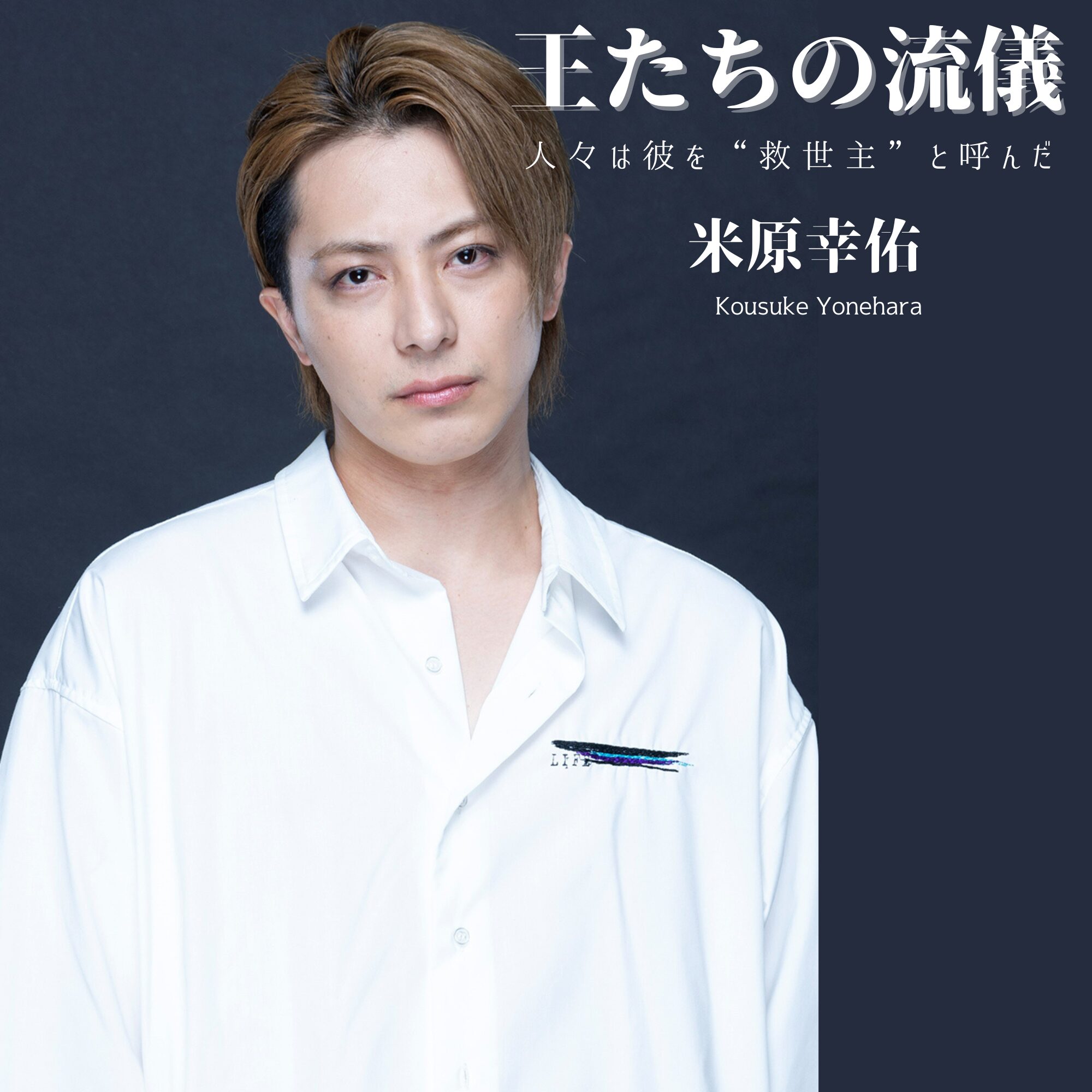
25.6.1 思いだす
王たちの流儀 Vol.2:米原幸佑
王ステシリーズの俳優に迫るSKETCH新連載企画 Vol.2-1
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
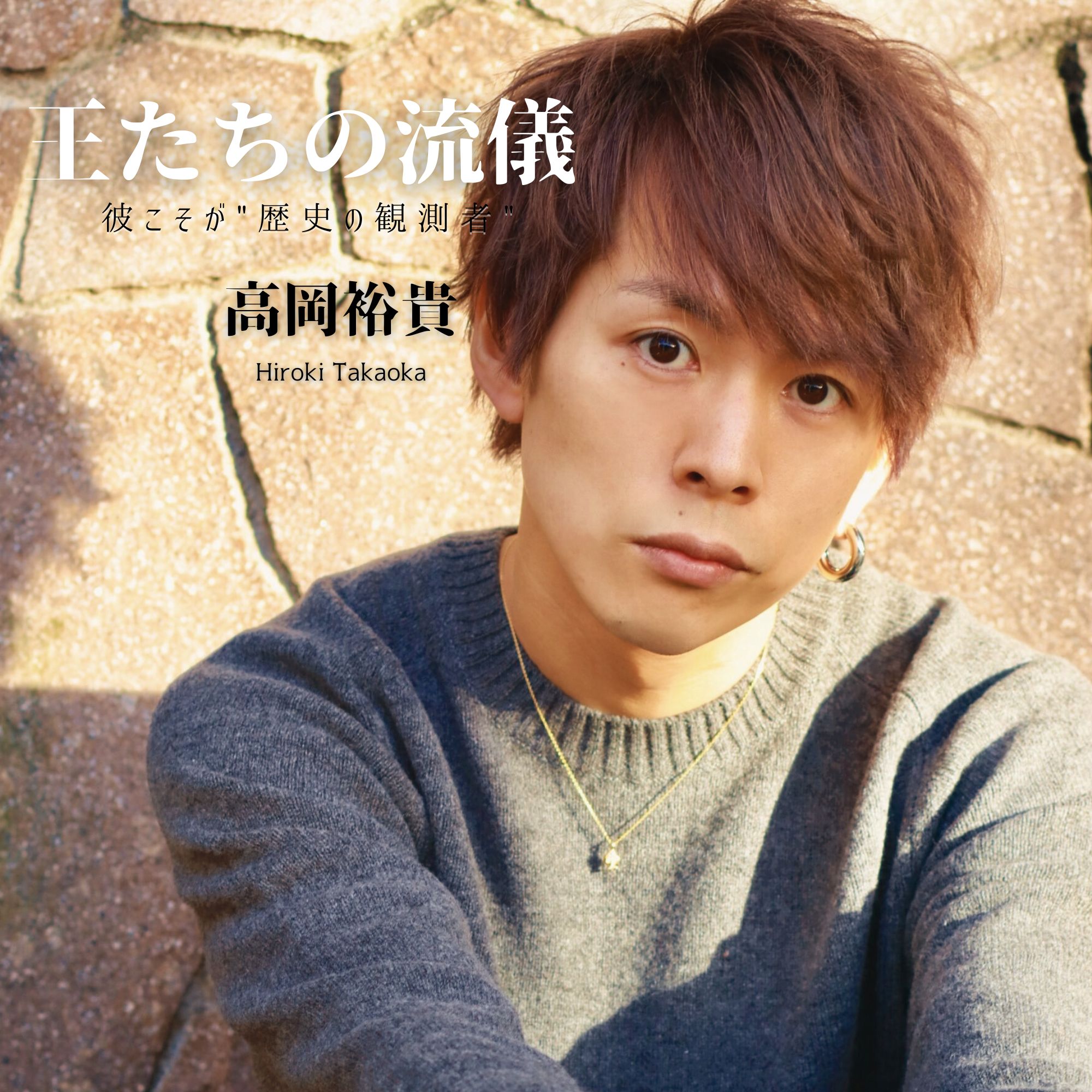
25.6.1 思いだす
王たちの流儀 Vol.1:高岡裕貴
王ステシリーズの俳優に迫るSKETCH新連載企画 Vol.1-1
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
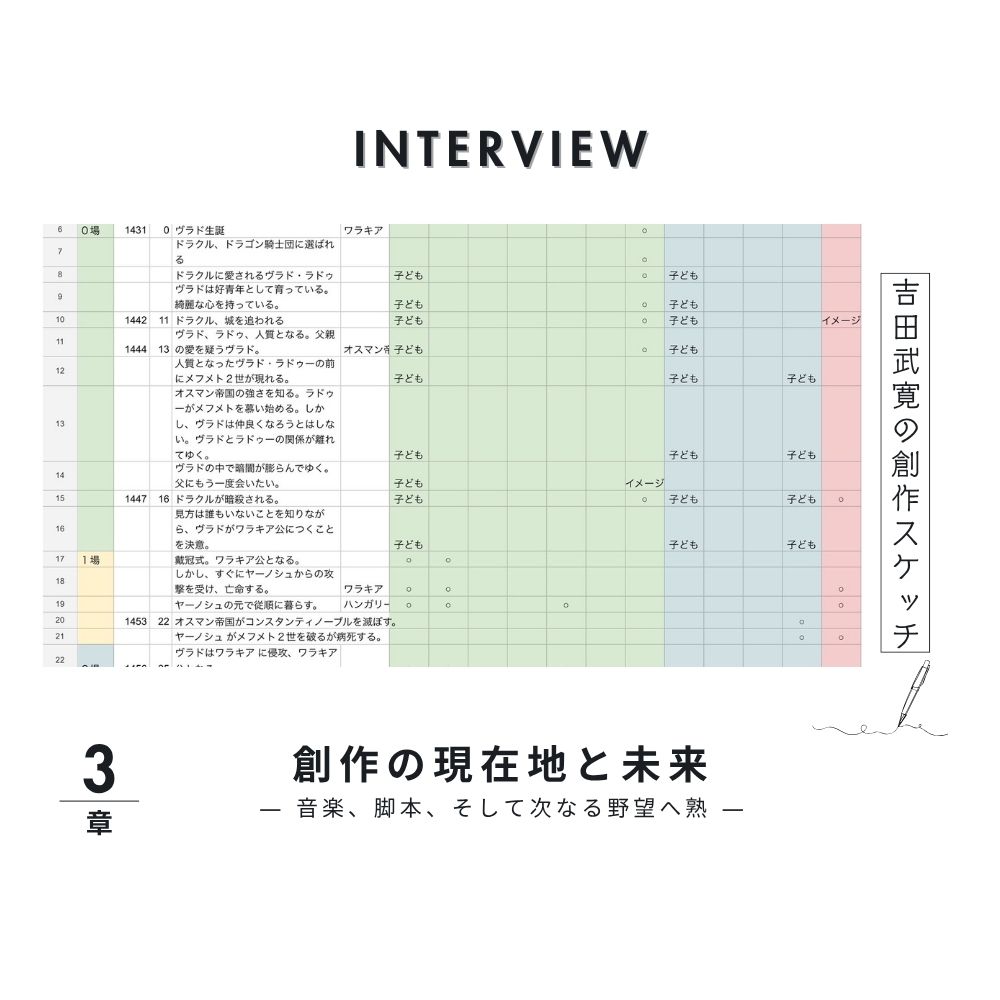
25.5.24 語りあう
【第3章】吉田武寛の創作スケッチ
創作の現在地と未来 ― 音楽、脚本、そして次なる野望へ
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
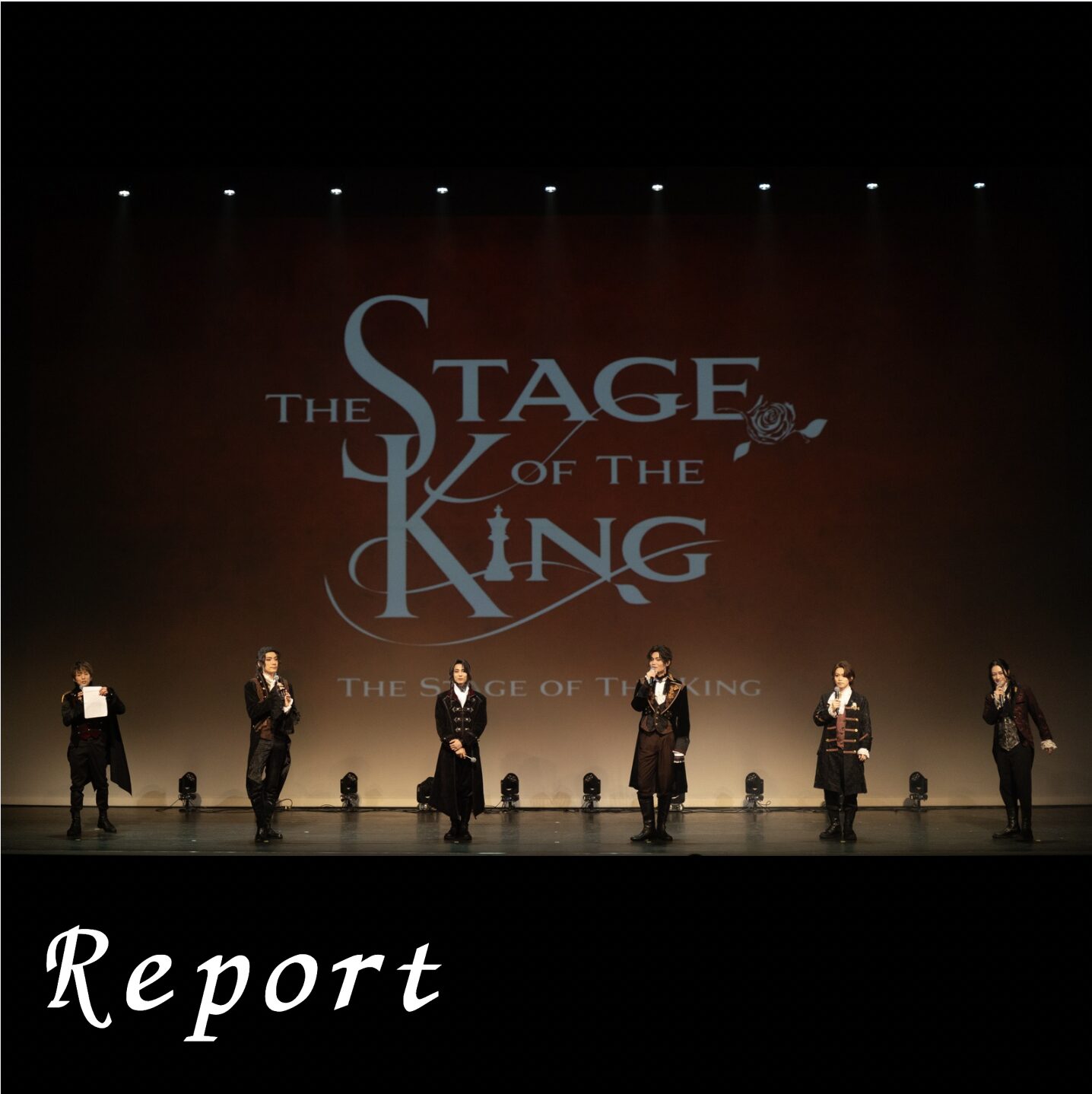
25.5.24 待ちのぞむ
『葬列の王』プレイベントレポート
──シリーズ第7弾へ、期待高まる一夜
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
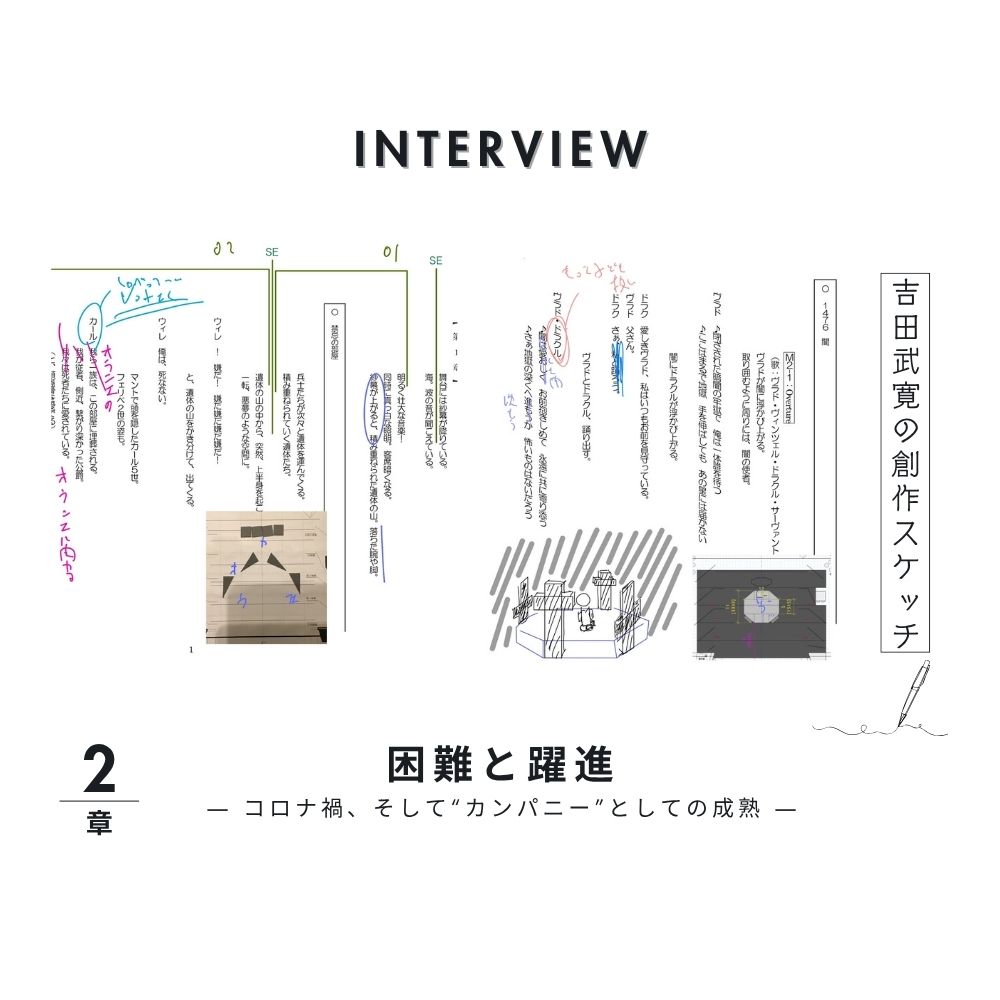
25.5.20 語りあう
【第2章】吉田武寛の創作スケッチ
困難と躍進 ― コロナ禍、そして“劇団”としての成熟
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

25.5.16 語りあう
【序章】吉田武寛 創作スケッチ
『王ステ』『女王ステ』の創作の軌跡 ― 吉田武寛の演出家像に迫る ―
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

25.5.16 語りあう
【第1章】吉田武寛の創作スケッチ
原点と試行錯誤 ― 『女王ステ』誕生から“演出家・吉田武寛”の確立へ
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
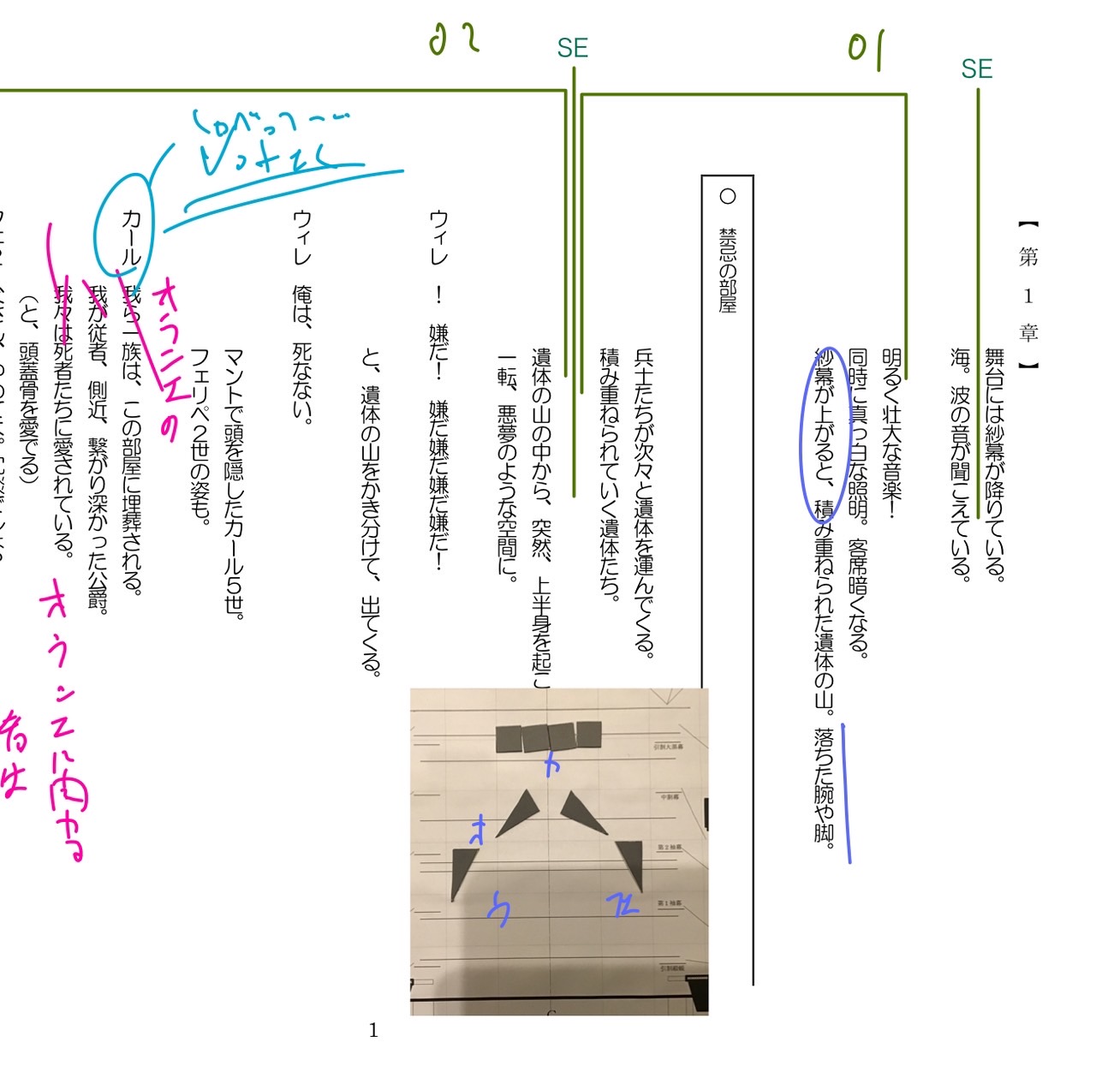
25.3.26 思いだす
「王ステ」三部作がDMMで配信
吉田武寛演出スケッチで振り返る「王ステ」三部作
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

25.2.5 ともに創る
畑宮ささの「世界観を歩く衣装展」体験レポート
まるで隣に立っているかのような「王と女王の衣装展」巡ってみたレポ
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
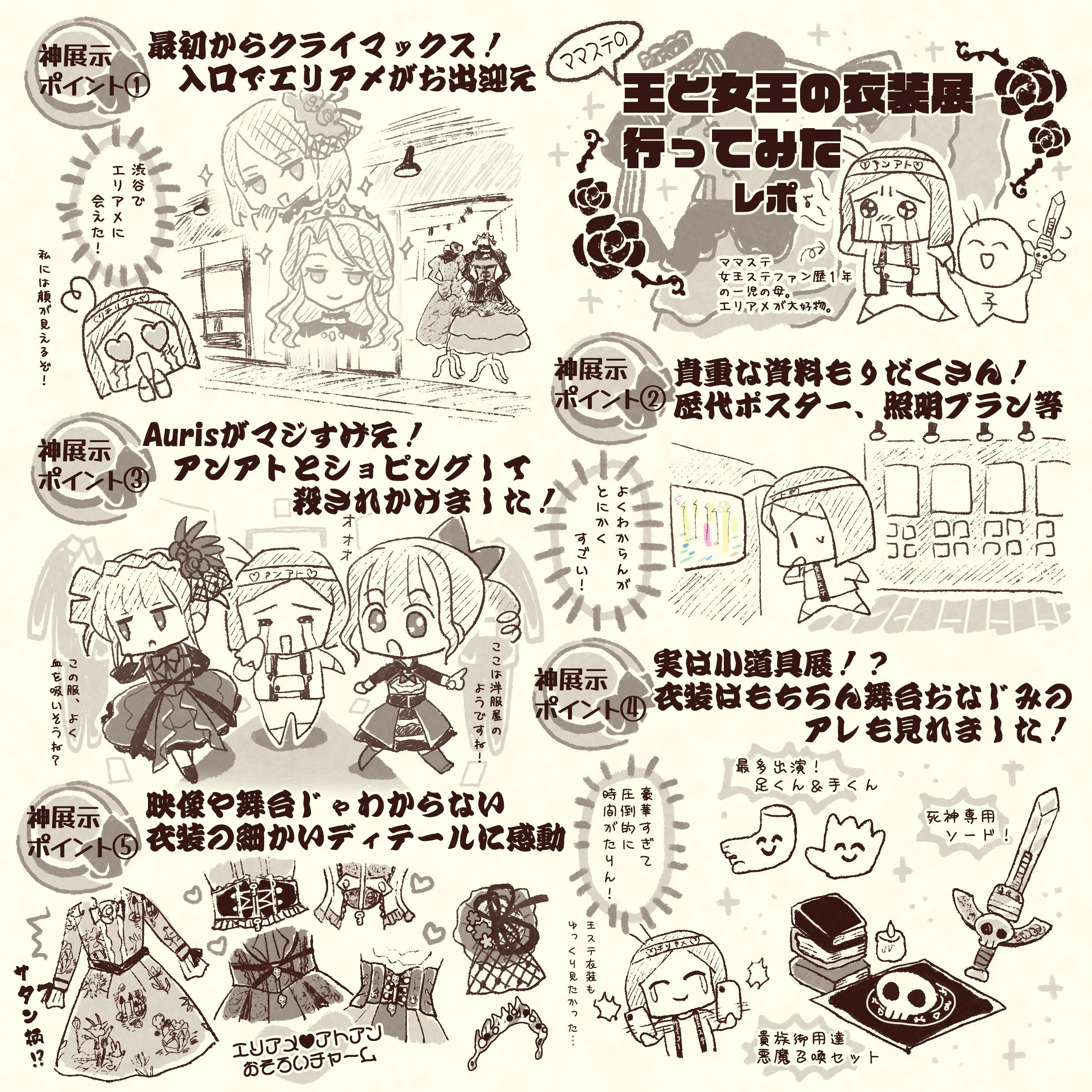
25.1.23 ともに創る
ママステの「耳が幸せな衣装展」体験レポート
渋谷にエリアメ降臨!豪華絢爛な王と女王の「お声付き」衣装展行ってみたレポ
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
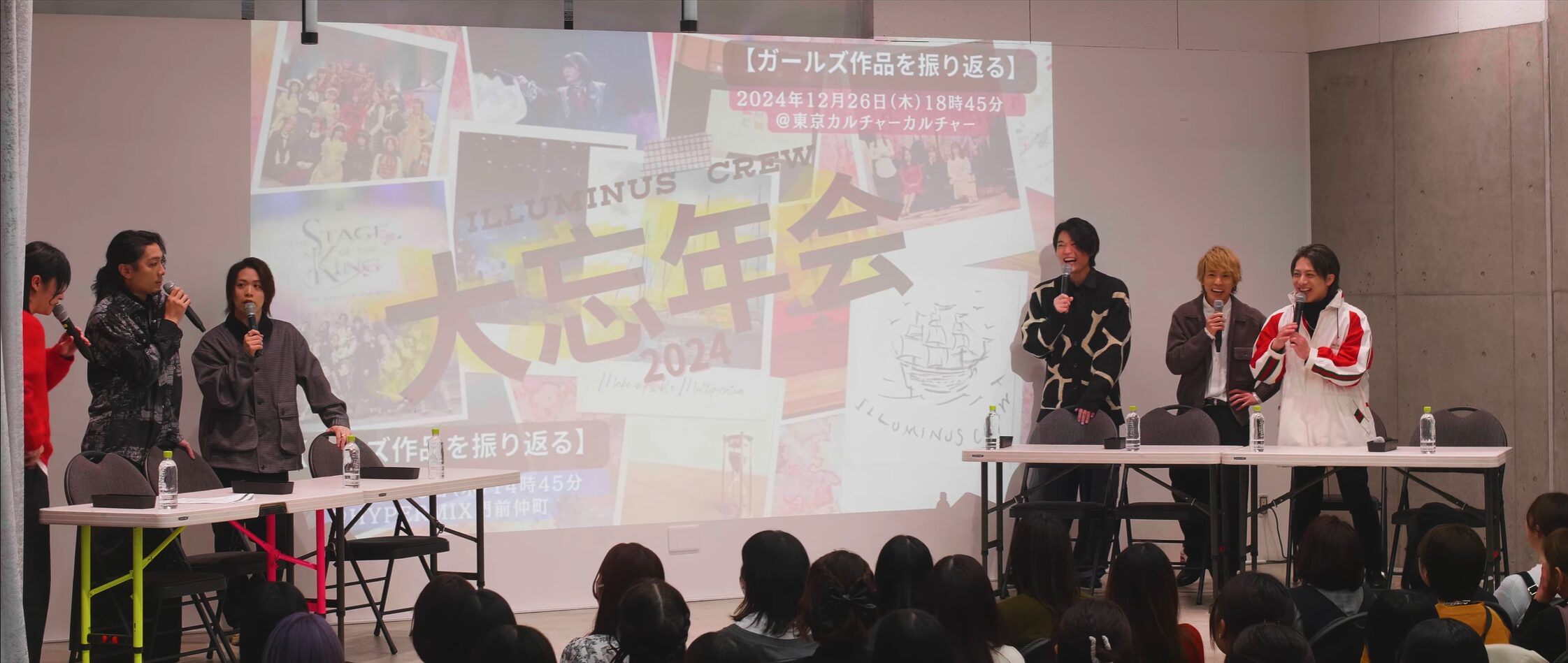
25.1.21 思いだす
イルミナスタークイズも解説!忘年会レポート
「ILLUMINUS CREW 大忘年会2024」レポート
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
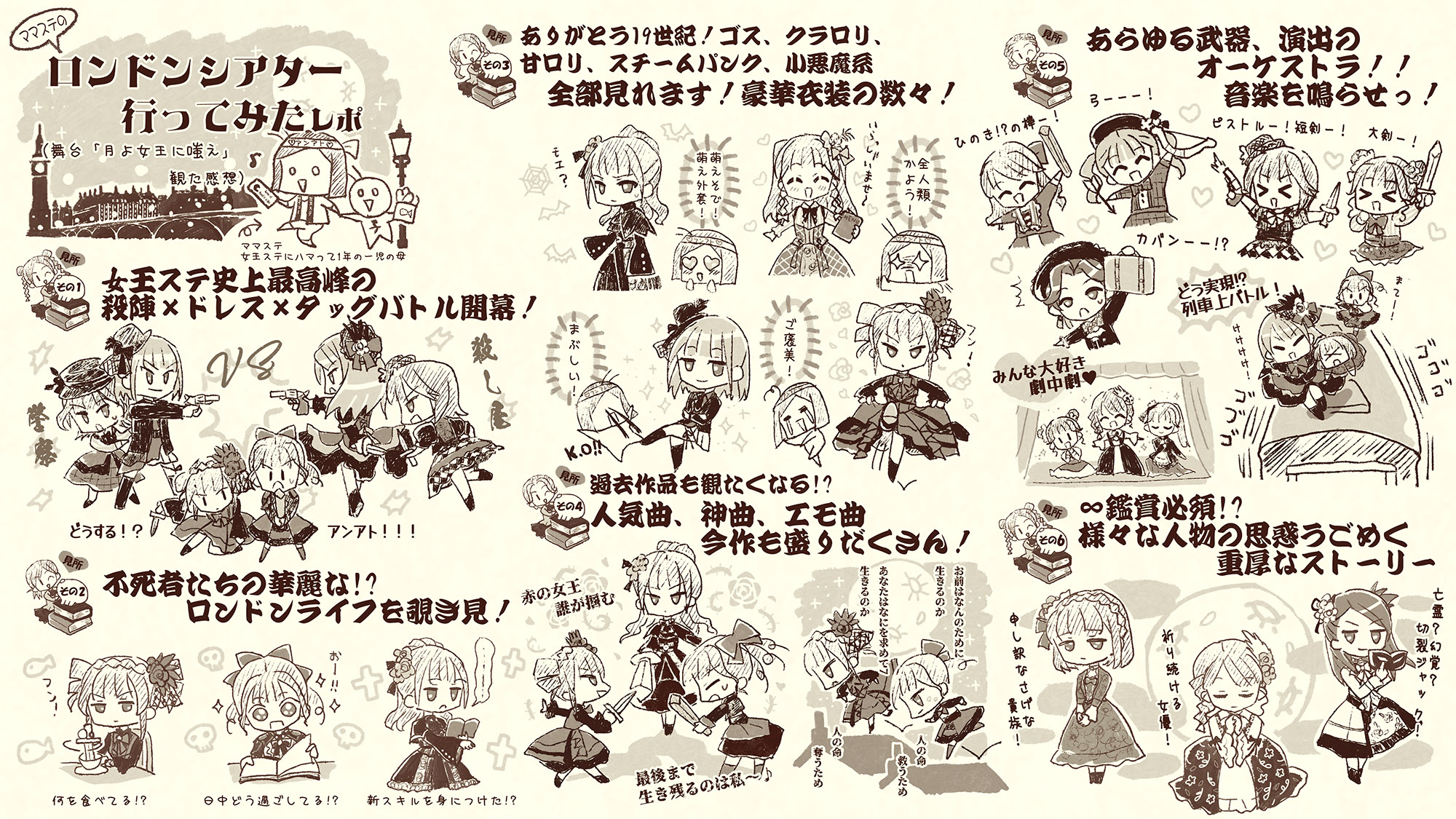
25.1.5 ともに創る
ママステの「月よ女王に嗤え」観劇レポート
女王ステにハマって一年の沼住民がロンドンシアター行ってみた!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
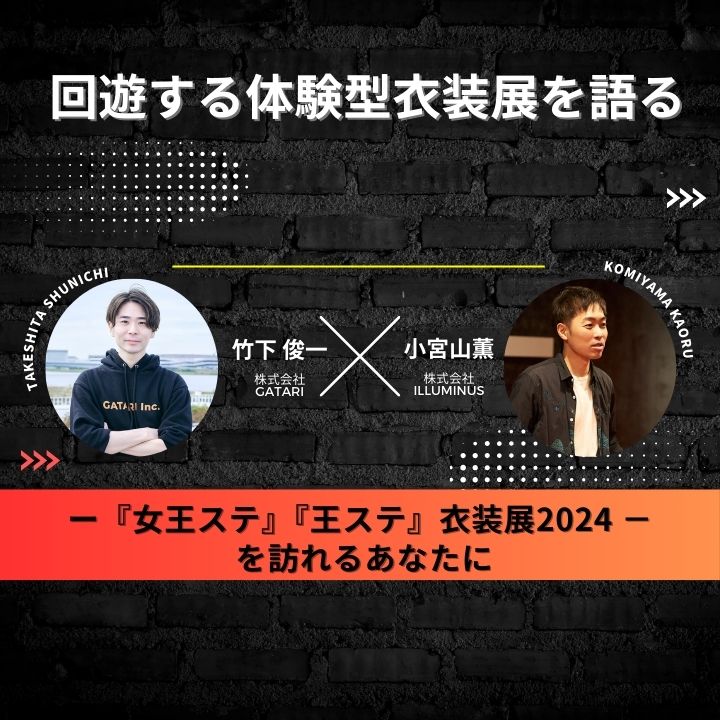
24.12.21 待ちのぞむ
『女王ステ』『王ステ』衣装展を訪れるあなたに...
回遊する体験型衣装展、−『女王ステ』『王ステ』衣装展2024 −を語る
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-


24.12.20 語りあう
#月よ女王に嗤え 楽屋トークを公開!
千秋楽終了直後の主演・演出家による楽屋トークを収録!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
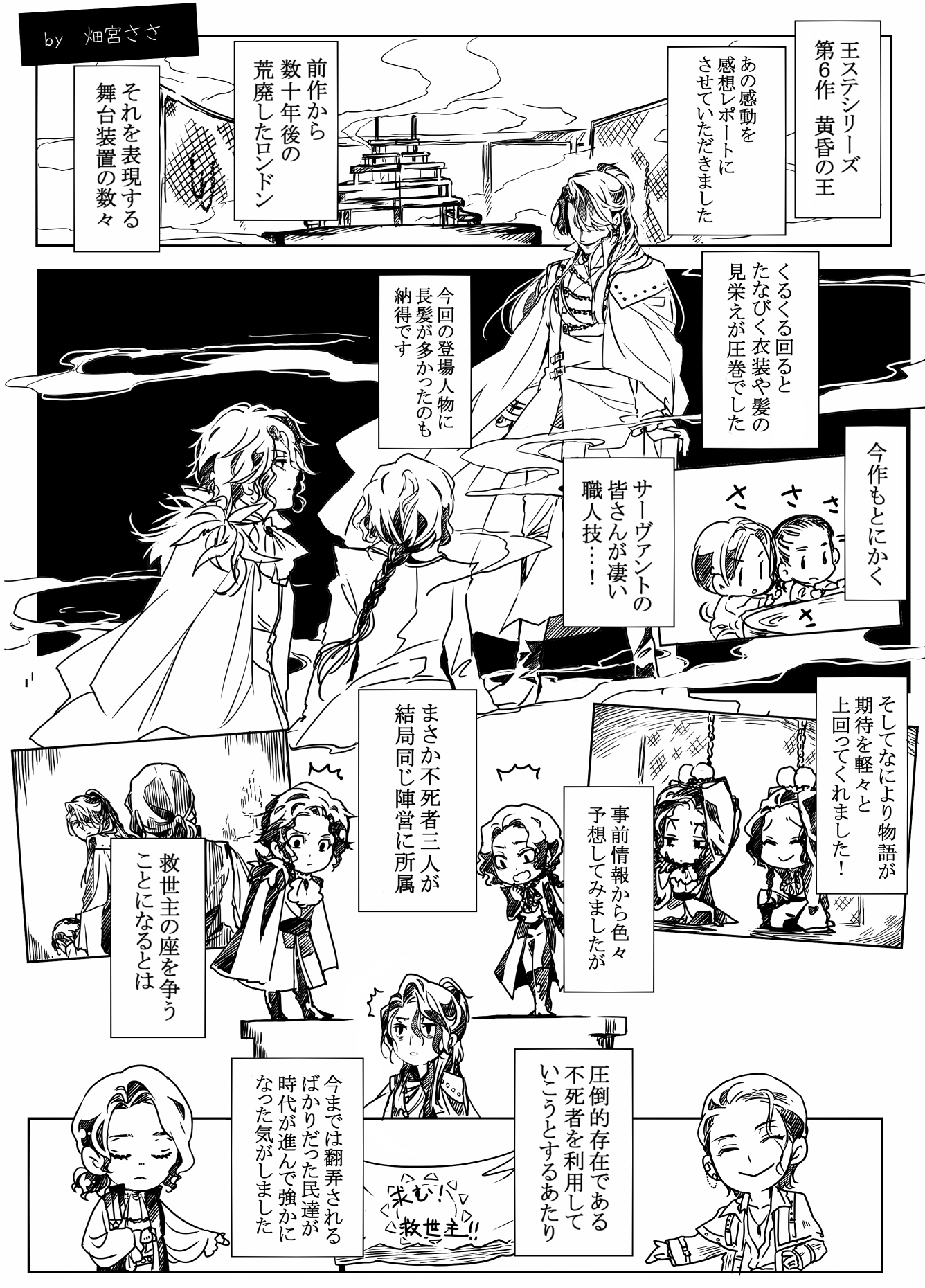
24.11.14 ともに創る
畑宮ささの『黄昏の王』観劇レポート
『蒼穹』出の新規が『黄昏』を観た感動をそのままマンガにしてみた!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

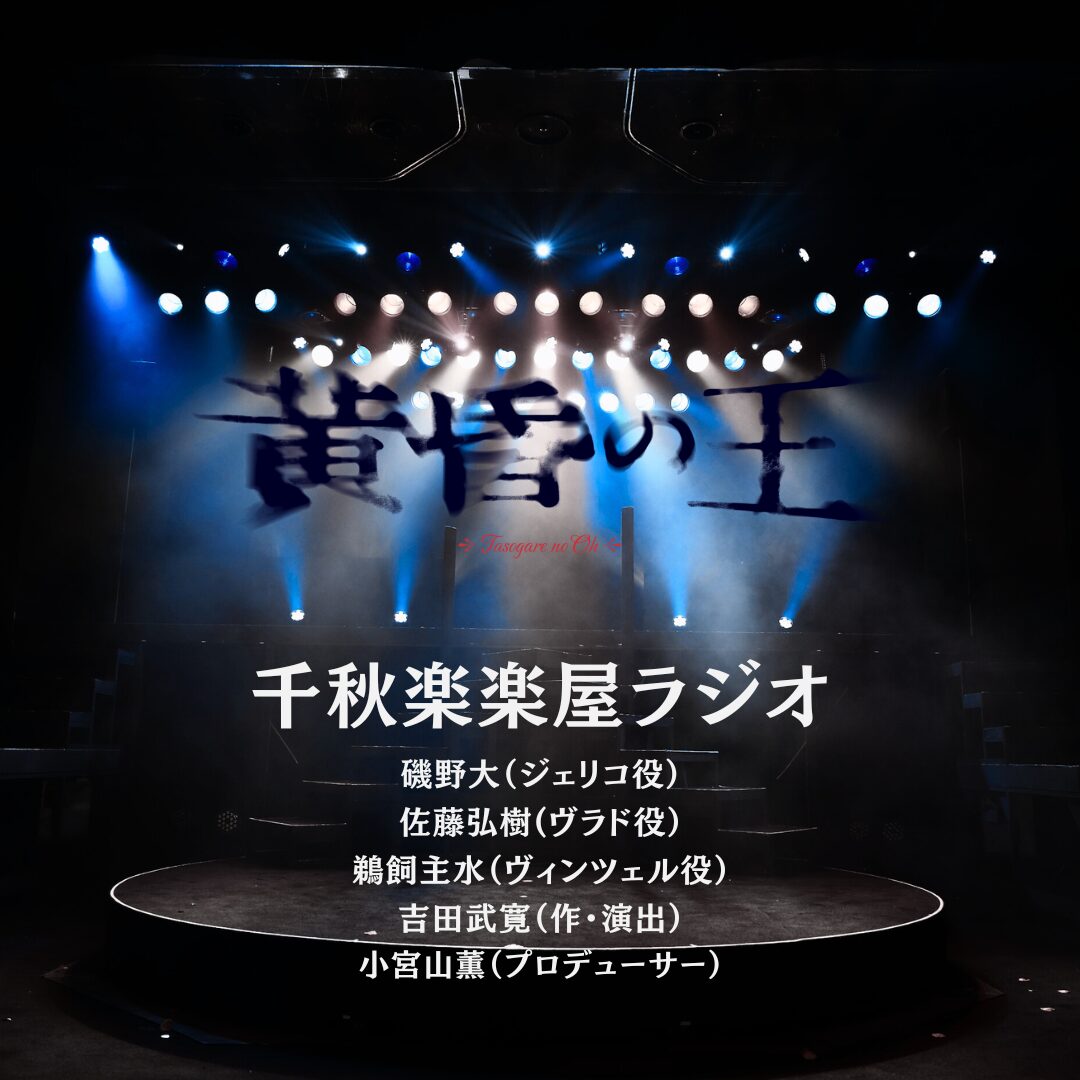
24.11.13 語りあう
#黄昏の王 楽屋トークを公開!
千秋楽終了直後の主演・演出家による楽屋トークを収録!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-


24.8.22 語りあう
舞台「黎明の王」千秋楽トーク公開!
磯野大、佐藤弘樹、鵜飼主水、吉田武寛が振り返る黎明の王
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-


24.8.22 語りあう
「楽園の王」千秋楽楽屋トーク公開!
沖侑果、大滝紗緒里、吉田武寛が楽園の女王を振り返る
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

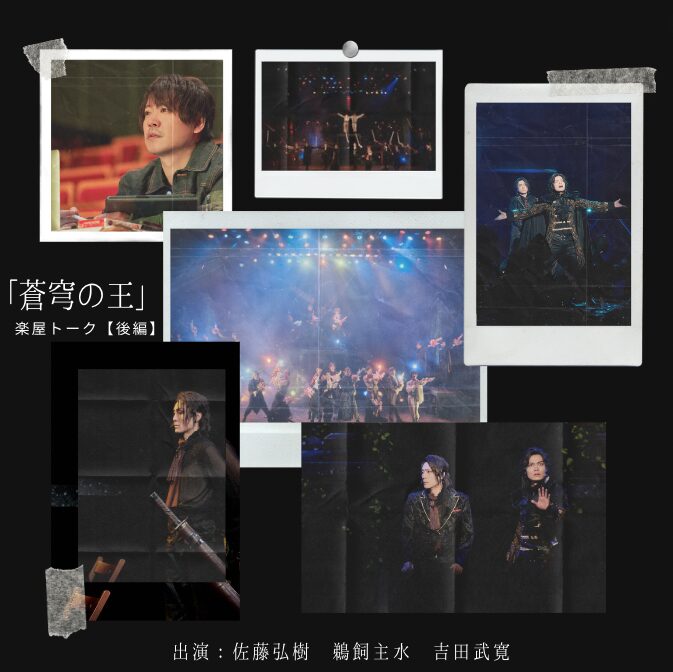
24.8.22 語りあう
「蒼穹の王」千秋楽楽屋トーク公開!
佐藤弘樹、鵜飼主水、吉田武寛が蒼穹の王を振り返る
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

24.8.22 ともに創る
王ステを愛しすぎた者たち
果てしない愛を、私たちなりの形で。様々な王ステ愛をご紹介!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

24.8.21 ともに創る
王ステの根幹を担う衣装のアップグレード
王ステシリーズ衣装サポーター2024募集
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

24.8.21 ともに創る
ママステの「楽園の女王」観劇レポート
「星よ」新規がバタヴィア号乗ってみた!-「楽園の女王」観劇レポート-
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
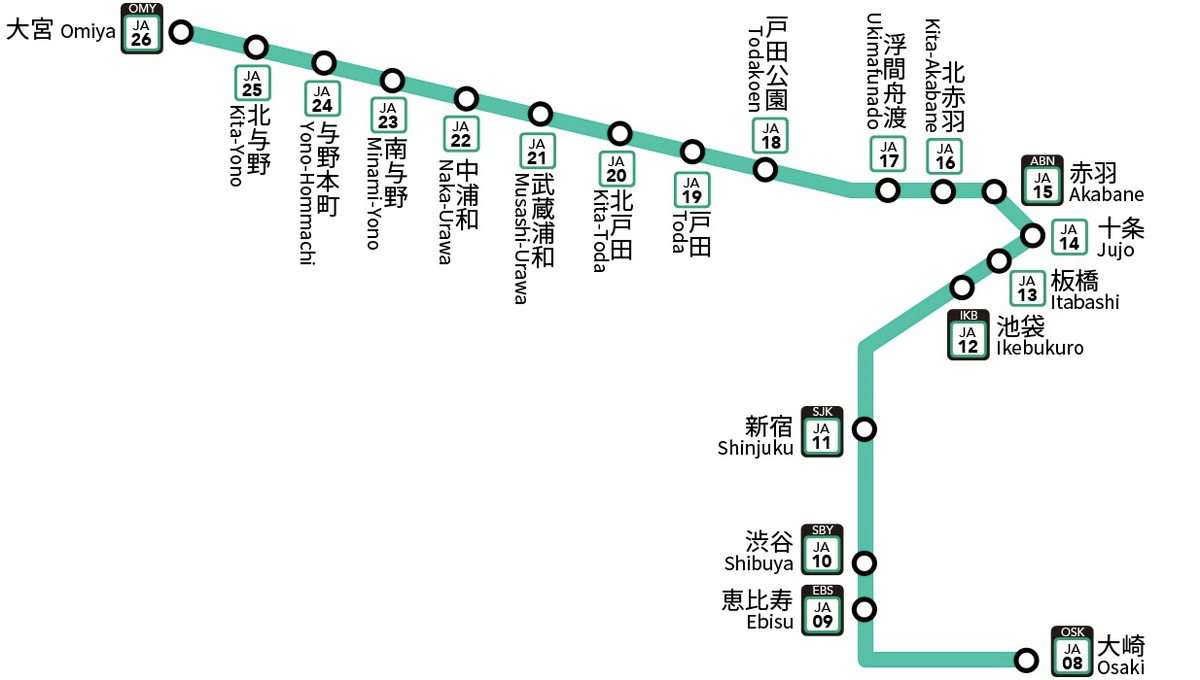
24.6.25 待ちのぞむ
Road to 六行会〜もう一つの最寄駅〜
イルミナスマニアのみが知る!?六行会ホールへの伝説の"大崎ルート"をご紹介
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
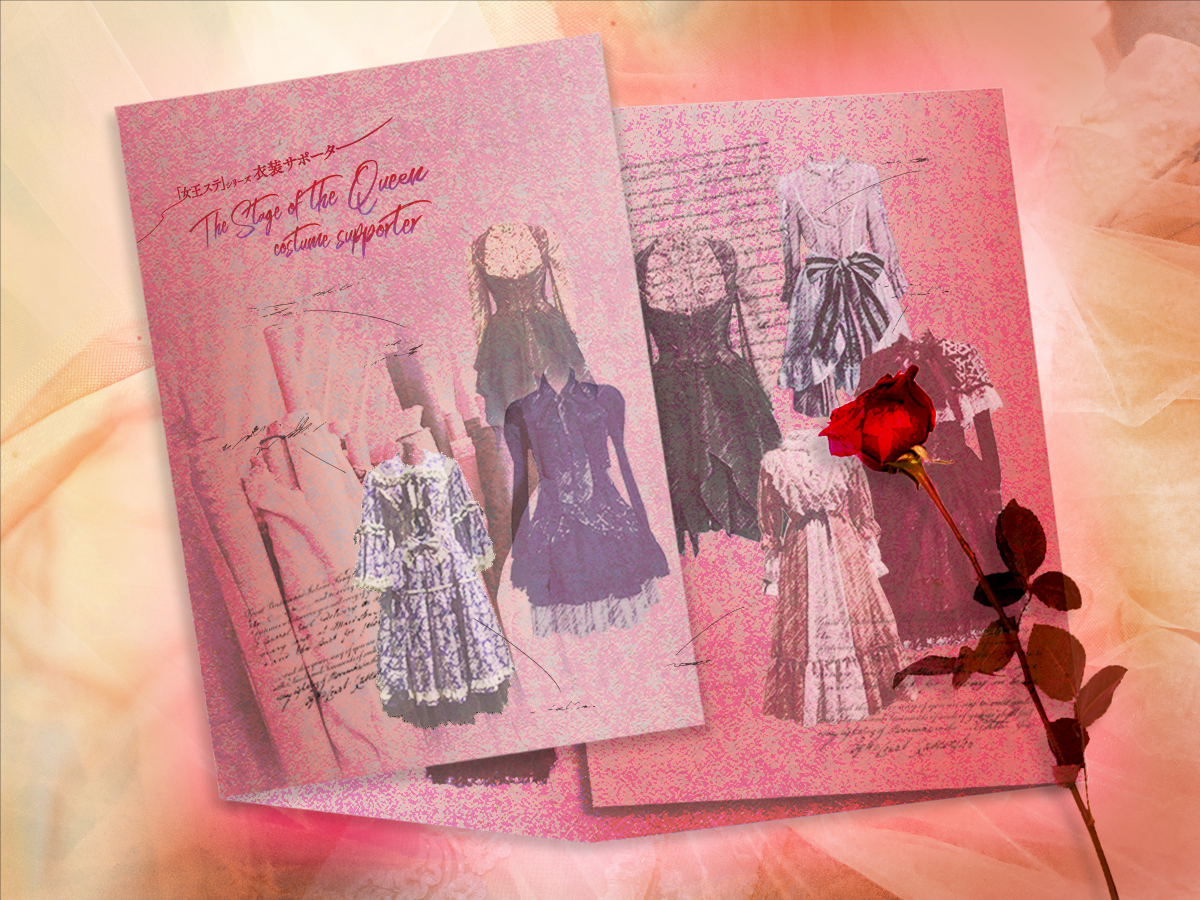
24.6.3 ともに創る
女王ステの根幹を担う衣装のアップグレード
女王ステシリーズ衣装サポーター2024募集
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
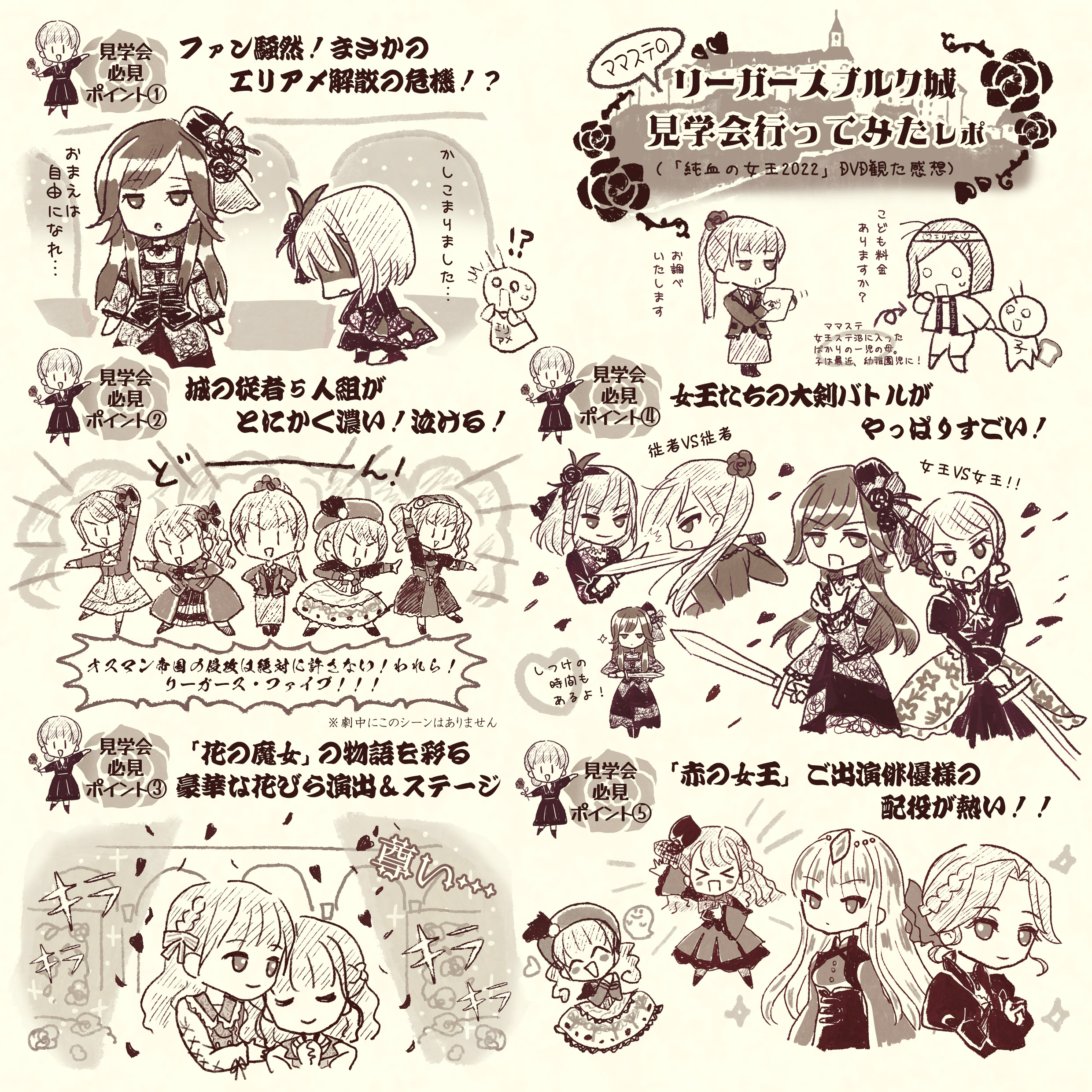
24.5.28 ともに創る
ママステの「純血の女王」鑑賞レポート
『星よ』新規のリーガースブルク城見学会レポ!~『純血の女王2022』観てみた!~
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

24.4.30 ともに創る
蒼穹の王FA展 in SKETCH
この愛こそが、芸術だ!蒼穹の王ファンアートご紹介!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

24.4.25 思いだす
この封鎖された村で、何があったか知りたいか?
『蒼穹の王』魅力的なファンのポストを運営がピックアップしてみた!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
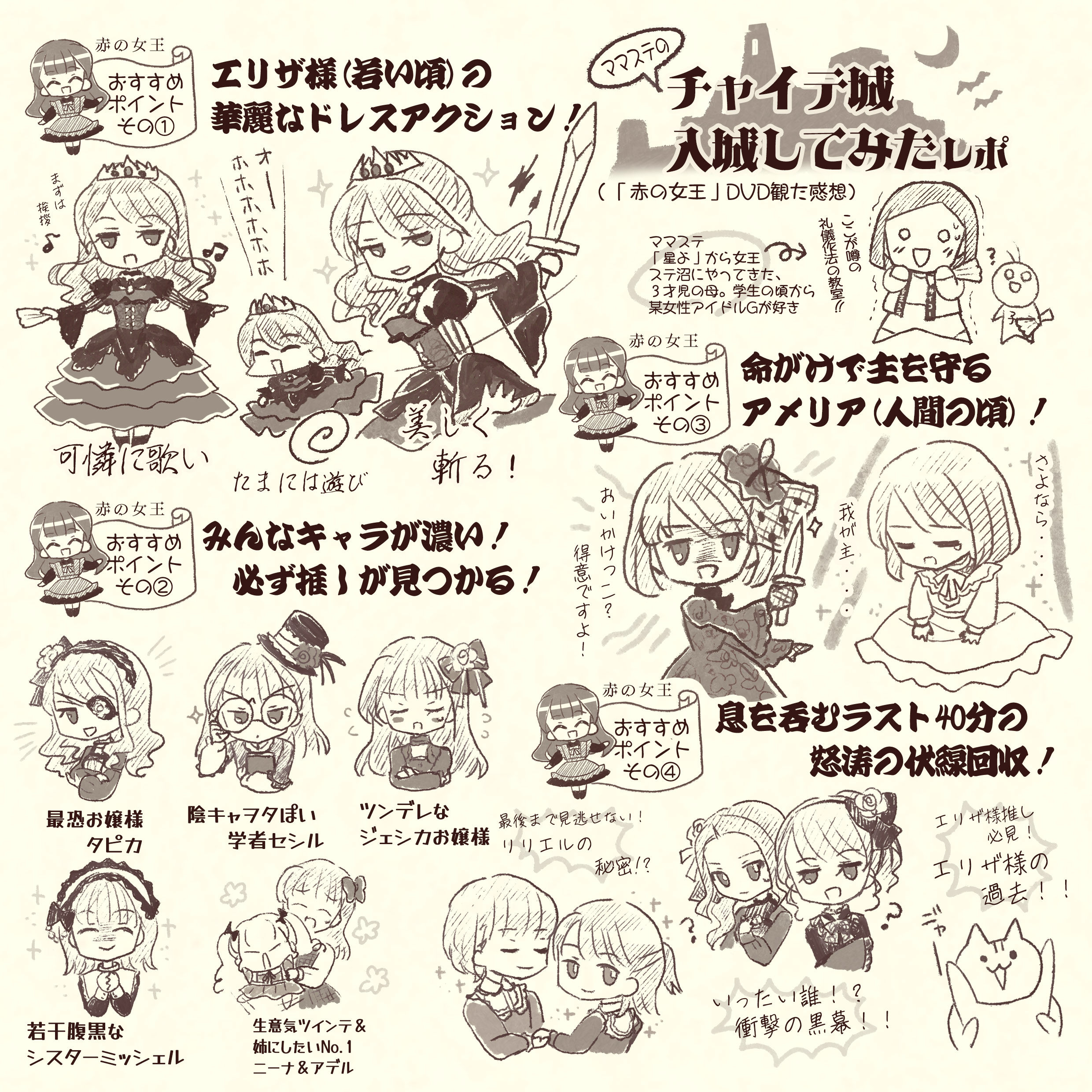
24.3.7 思いだす
ママステの「赤の女王2022」観てみた!
「星よ」新規のチャイテ城入城レポ!「赤の女王2022」観てみた!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

24.2.20 身につける
「王ステ」と共にある生活
王ステファンの推し活を彩る「アクスタ」・「アクキー」活用術をご紹介!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

24.2.7 思いだす
あの夜の宴を、もう一度
『女王ステ』の世界観を彩る名曲たちのスペシャルライブ公演!Blu-ray販売中!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
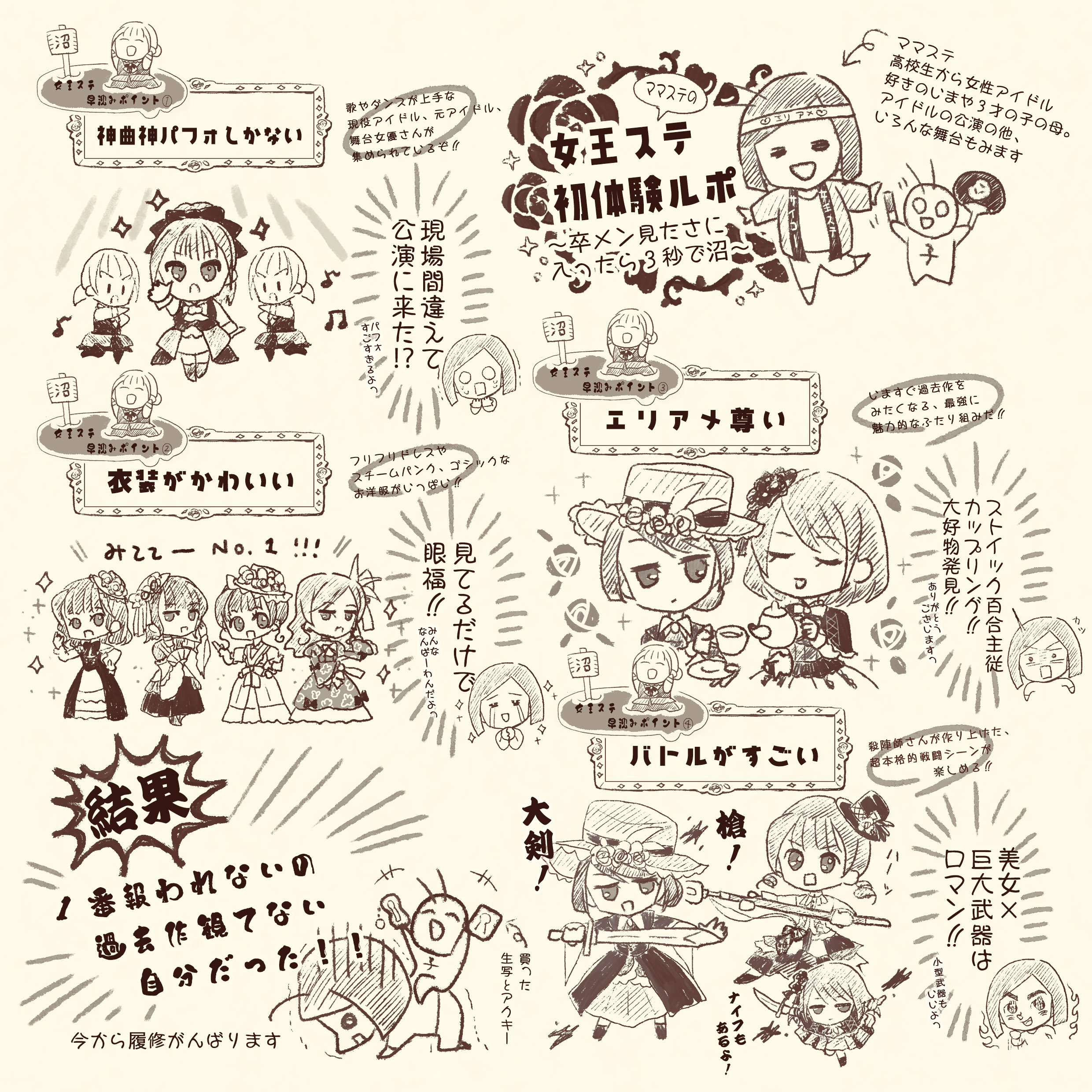
24.1.26 思いだす
ママステの女王ステ初体験ルポ!
「女王ステ」初体験ルポ! アイドルファンが出会った、初めての女王ステの衝撃
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

24.1.16 思いだす
黎明の王Blu-ray 惨劇の夜を、何度でも
王ステ初のBlu-ray登場!舞台「黎明の王」惨劇の夜を、何度でも
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

24.1.1 思いだす
吉田武寛の演出スケッチ vol.2
女王ステシリーズ『星よ女王に堕つ』の吉田武寛の演出スケッチを特別公開!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
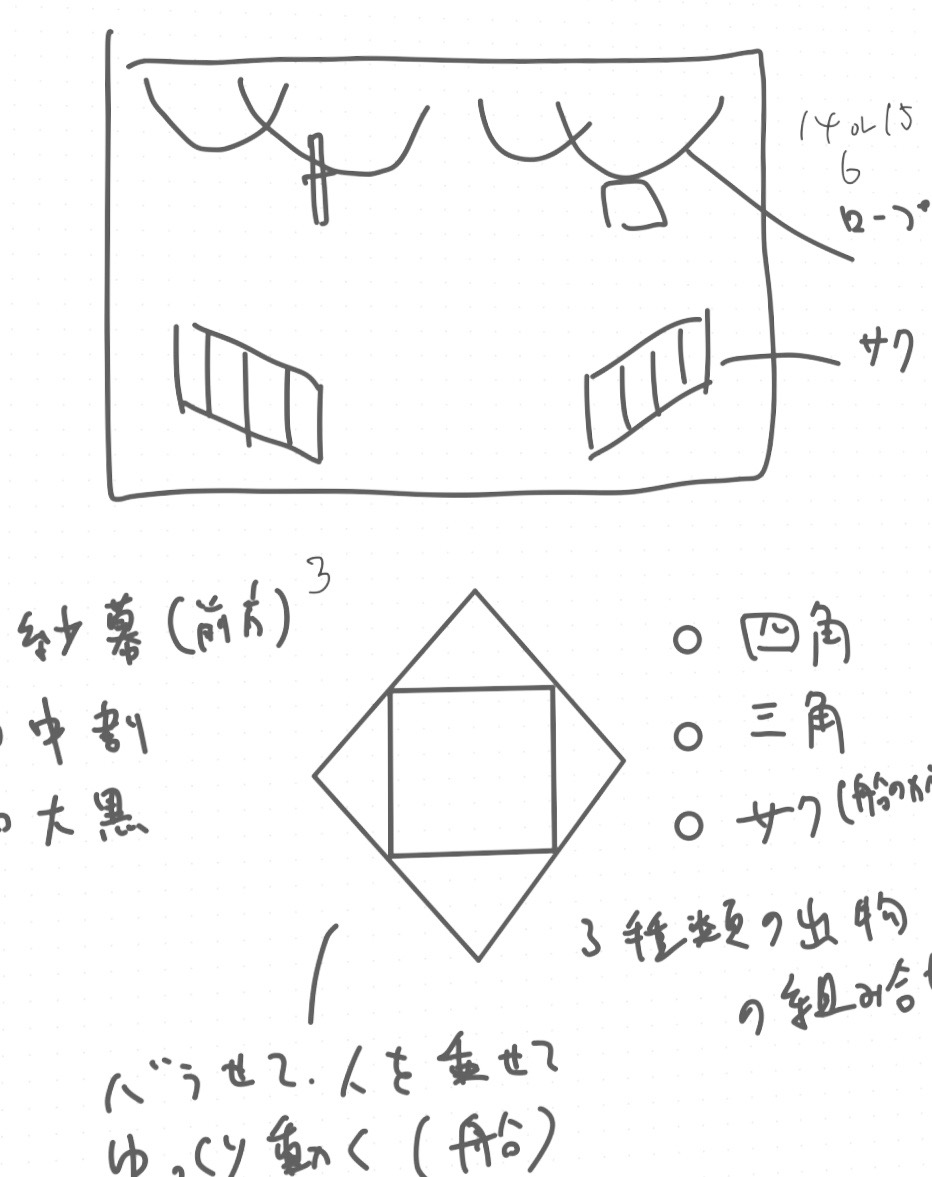
24.1.1 思いだす
吉田武寛の演出スケッチ vol.4
王ステシリーズ「屍の王」の吉田武寛の演出スケッチを特別公開!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-

24.1.1 身につける
王ステを身にまとう
王ステオリジナルパーカーメイキングエピソードを公開
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH
-
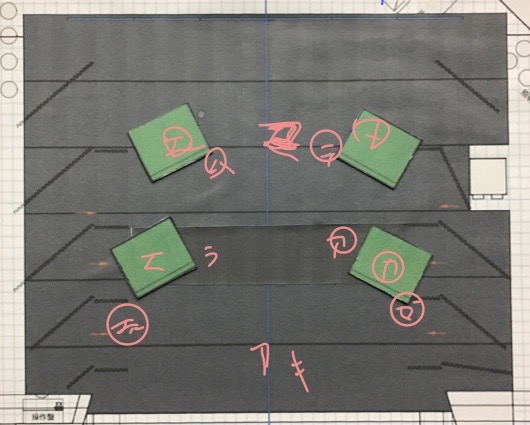
24.1.1 思いだす
吉田武寛の演出スケッチ vol.5
吉田武寛の演出スケッチ公開!女王ステシリーズ「女王虐殺」DVD販売中!
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE
SKETCH