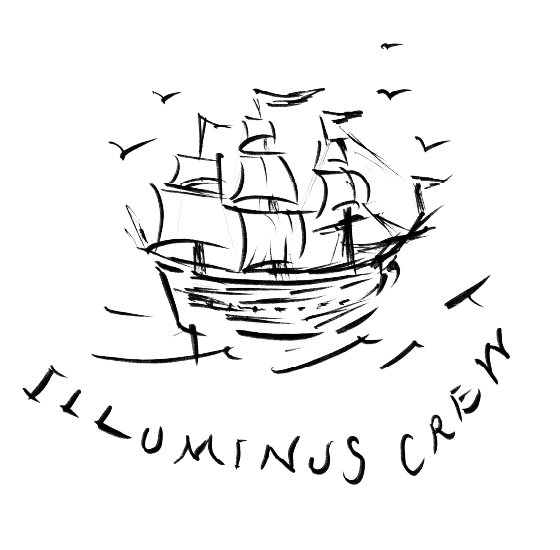25.10.1幾原邦彦×淡乃晶 対談 『春琴の佐助』が生まれた舞台裏

幾原:そうだね。別にこの舞台のことだけではなくてね、いいセリフとかかっこいいセリフとかができた時が逆に危険な時だよね。僕、色々舞台をこれまで人生の中でもかなり見たけど、体験型の方が僕は好きなんだよね。
淡乃:なんかフレーズが決まりすぎると、フレーズに意識を持ってかれるって感じなんですか?
幾原:いい話なんだなと思った途端に、ちょっと終わっちゃうっていうのかな。
淡乃: 他人事になっちゃう。
幾原: フィクションのドアがなんか急に見えちゃうっていうのかな。
淡乃:あまりにも作られた言葉だからってことなんですかね。
幾原:そうかもしれないね。現実の世界だと、そんなにいい言葉が交わされるってことがないじゃないですか。 もちろん、フィクションで癒されるっていうことはあるとは思うんですよ。だからそれ自体は別に否定されるもんではないと思うし、僕もそういうものはあっていいと思うし嫌いではないんだけど。たまたま僕がなんか最初の体験がそういうところ(体験型の舞台)から入ってきたので、 どうしてもそこが自分の基本になるっていうことなのかな。こういうことを僕がやり続けたいと思ってるわけではないんだけど、多分『春琴の佐助』は最初の舞台だったんで、そこは気になったということだと思うね。特に、最後どうするかっていう話でやり取りがあったじゃないですか。わかりやすく観客に「こういうお話でした」っていう風に提示するべきなのか、そうじゃないのかっていうね。本当に迷ったよね。
淡乃:そうですね。僕があげた初稿は綺麗な収まりにはなってました。
幾原:そして2稿目に淡乃さんが「物語主体で終わるんじゃなくて、観客の心に何か残す、ドラマが欲しい」みたいなことで、ある会話を書いたわけだよね。それがね、すごくいいセリフなんですよ。でもそうなると「この話はこういう話でした」っていうピリオドが、それはそれでついてるっていうさ。 宙に投げるつもりだったんだけど、ちゃんと回答として用意してるっていう風にみえてしまう。
淡乃:逆にお話を期待させちゃいましたね。幾原さんとあらためて終わり方を話し合って。
会議して出たものは、かなり収まらない、「こんな終わり方なんだ…!」っていう感じで、すごくワクワクしました。
幾原:今リハ中だからね、どうなるがわかんないけど、また最後の最後の最後で、淡乃さんや北島さん※3とかが、僕の意見を面白いって言ってくれて、採用してくれてるわけじゃないですか。「大丈夫か?」って言いたくなる方向だよね。
淡乃:でも、このフィールドでしか見られない幾原さんの表現というか、側面みたいなのが、今回出たら面白いんじゃないかとはずっと思ってはいて。だからこういった表現もあるというパターンとして世に出せることが瑞々しくて。今だからできる表現を幾原さんが前向きにやってくださってるので、僕らもトリッキーなことができていますね。
幾原:本を上げる前は、これを物語として伝えようとすることをしてしまうんじゃないのかっていう風に考え込んでしまって。その意味だと、今回の構成は良かったかなと思うね。
淡乃:いいポイントが体験的なボルテージになっていて。ワードがいいとか、ひとつだけじゃなくなっている。
幾原:まだ結局これ作り中なんで色々混ざってる状況ですけど、これがいいのか、それとももうちょっと整理整頓したものがいいのかはやってみないとわからないか。
淡乃:参照元がないみたいなことを今行おうとしているっていう形なんですかね。
幾原:こういう試みが他でもあったのかどうかってのは知らないけど、少なくとも、僕が今まで聞いた朗読劇では、こんな表現はなかった。こちらが意図してるように最終的にステージの上で表現できるかどうかって、まだ全くわからない。 ただうまく表現できたとしたら珍しいものにはなってると思う。これを支持してくれる人がいるならこの次も何か考えられるってことはあるのかもしんないけどね。
淡乃:実験劇場っていう提案でもありますしね、今回の企画は。だから、劇場に来てもらうお客さん、配信で見るお客さんは、1ページ目というか。本当に最初の体験者ですね。
幾原:もちろん考える瞬間をなるべく作りたくないとは言いつつも、心には残ってほしいと思ってるわけです。劇場に来た人の心に残れるかどうかっていうことだよね。みんながこの作品をね、体験してくれて、 すごい良かったとか、すごい心に響いたっていう風なね、気持ちをね、持って帰ってもらえるかどうかですよね。
淡乃:楽しみなのは、今まで自分がやったことないくらい攻めたシーンというかも一応あって。繰り返す(リフレイン)のところとか。
幾原:あれ、やったことないの? にしてはすごい大胆だよね。
淡乃:ああいう崩しがないと、お話として見ちゃうんじゃないかなって。普通に進めるとどうしても、展開と事件が起こってそこを期待するようになっちゃうので。
幾原:そう、ラストシーンは、あの言葉の繰り返しで、観客は不安になったまま、佐助と一緒に連れていかれる…春琴に。その観客の体感時間の不安さみたいなのはね、アクセントとして良いとは思うね。あのリフレインの長さは狙ってるの?
淡乃:体感ではあるんですけど、ただリフレインして、若干麻痺してきて、慣れてきて、で、まだやめないでくれって思うタイミングぐらいまではやりたいなっていう。
幾原:結構ね、これ壊れるんじゃないのかとかこれ破綻するんじゃないのかっていう、その感じが面白い。
淡乃:お話を感情と体験にするために、2場の頭をいきなりビンタ音ではじめて体感に寄せてるんですけど、そこから次の3場でまたお話が来たら、拍子抜けしちゃうというか。春琴って本当はミステリアスでその裏側をあまり語られないんですけど、あえて感情的にするために、(3場で)内面を語るモノローグを挿入して、お話とは違う軸ですよっていう風にした上で、そのリフレインが始まり、音だけを聴く時間に繋がっていくことで、 物語的なものを解体していけたらなという狙いはありました。
幾原:(リフレインの)あのシーンによって、役者の肉体的な部分だけがむき出しになってくるわけじゃないですか。 声の芝居だけど、肉体がむき出しになっていくわけだよね。それを体験する時間になってるわけだよね。そこが観客にとっては、不安であるのと同時にリッチな時間だと思うんだよね。そこはすごく良いと思うよ。
淡乃:なんでしょう。お話ではないところで、その場で発生された声がずっと続くっていうのは事件性もあるなっていう。今回は収めるよりかはやり切る方向でやってみようっていう方針があって。
幾原:発見がね、色々ある。あるよね。そうなんだとか、そうなるんだとか。

※1:百合音声サークルSukeraSonoからリリースされている「終末」をテーマにした音声作品。各種配信サイトで販売中(2024年10月現在)
※2:この対談はアンダーキャストとの稽古後に収録してます。
※3:北島とわ。『春琴の佐助』に音楽・live DJとして参加しているサウンドアーティスト。淡乃晶と長年クリエイションを共にしており『イルミラージュ・ソーダ』のサウンドアートも手がけている。