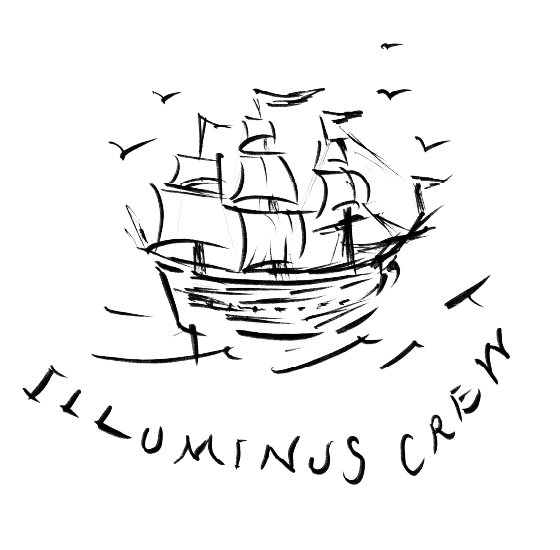25.10.1幾原邦彦×淡乃晶 対談 『春琴の佐助』が生まれた舞台裏
イクニプロデュース Reading in the dark『#愛の地獄変』の上演を記念して、
過去に上演された『#春琴の佐助』の再配信が決定いたしました。
これにあわせて、総合演出・脚本を手掛けた幾原邦彦と、脚本・演出を担当した淡乃晶による対談を特別に公開いたします。
作品の立ち上げの経緯から、「Reading in the dark」シリーズに込められた意図、さらには『愛の地獄変』とのつながりに至るまで――創作の裏側をたっぷりと語った内容です。
再配信とともに、ぜひ本対談を通して『春琴の佐助』の魅力を改めてご堪能ください。

淡乃:まず僕と幾原さんの出会いについて話した方がいいかなと思うんですが…。僕が携わった2022年6月にリリースした音声作品『イルミラージュ・ソーダ 〜終わる世界と夏の夢〜』※1(以下:『イルミラージュ・ソーダ』)という作品を幾原さんが聴いてくださったのがきっかけでしたね。
幾原:ASMRっていうジャンルを聴いたのも初めてだった。『イルミラージュ・ソーダ』を聴いた時に、それがそのジャンルの中でどういう位置付けなのかもよくわからなかった。
淡乃:何に興味を持ってくださったんですか?
幾原:ドラマの見せ方っていうかな。オーディオドラマだから見せ方って言葉が適切かどうかわかんないんだけど。今まで聴いてきたいろんなオーディオドラマとちょっと何か違うなと思ったね。体験行為に近いような印象だったかな。音声作品が、何かを「体験する」っていう行為になっているあたりが面白いなと思った。
淡乃:物語がちょっと自分の話みたいに思えるような…?
幾原:そうだね。「探す」っていうディテールがあって、その「探す」という行為をユーザーが体験するような聴かせ方になっていて。それが物語とリンクしてユーザーもその物語を体験するってことになってるのが面白くて。それで作ってる人に興味を持って、淡乃さんに辿り着いた。
淡乃:僕は幼少期から幾原さんの作品の大ファンでございまして。音声作品をやってて、まさか幾原さんと出会えるなんて思ってもなかったです。そこから「なにか新しいものを作ってみないか?」という流れになって。
幾原:音声で何か、舞台とかやれないか?みたいなことを結構話し合った。 半年以上話し合ったよね?
淡乃:はい、おそらく一年近く(笑)。最初は音声作品を作ろうという企画だったんですけど、揉んだ結果、舞台表現や朗読劇をベースにしたもので作品を作ろうとなっていきましたね。幾原さん的に朗読ってどういった表現だと今まで感じてました?
幾原:僕も何度か朗読劇は観ていて、舞台上で役者の方が何か本を読み聞かせするというイメージだったね。でも淡乃さんと一緒にやると、そことはちょっと違うものを表現できるのかなとは。
淡乃:読むっていう行為から体験的なところに結びつけられる感じですかね。
幾原:そうだね、観ている、聴いている観客が物語を体験するみたいな作品がいいと思ったの。
淡乃:幾原さん的には、アニメーションや他の媒体の作品でもその体験的な視点って今まで意識されていたんですか?
幾原:どうかな。したのかもしれないんだけど…。
淡乃:幾原さんの作品って、自分の実生活と重なり合ったり、ふとした瞬間に刺さる部分があるんですよ。それはただ映像作品を観るというわけじゃなくて、お話を超えた表現というか、体験的な仕掛けが幾原さんの作品の中にはあるなと思っていて。
幾原:正直なところ、半年以上前、最初の方はなんかどうしても、僕の中でしっくりこなかったんだよね。最初はオリジナル作品でやろうとしていて。でも、それが何かあんまりうまくいかなくて。
淡乃:確かに、最初そうでしたね。オリジナルのプロット作業は進んでいたんですが、朗読としての意味とか、体験的な設計のコアがなかなか決まらなくて。
幾原:どこで『春琴抄』の話が持ち上がったんだっけ? なんか突然だったよね?
淡乃:僕、覚えてるんですけど、話し合いに詰まって連絡が一瞬だけ途切れた期間があった後、幾原さんとご飯を食べに行ったんですよ。そこで幾原さんが「『春琴抄』はどうだろう」って急に言い出したんですよ。
幾原:そうだっけ? ということは、おそらくその前に僕の方では「『春琴抄』はどうだろうか」って思ってたってことだよね。そこで突然思いついたわけではないよね(笑)。
淡乃:そうですよ!『春琴抄』は、春琴が盲目だから、同じように見えなくて暗いところで観客が音を聴くという体験が朗読とマッチするんじゃないかっていう、企画の核心みたいなことを幾原さんがもうすでに考えてくださっていましたね。
幾原:で、実際そこに突き進んで 我々はやったわけだけど、そういう意味では正しかったかなと思います。

淡乃:現状、稽古場で見てて、幾原さん的にはどんな感覚ですか?※2
幾原:うーん、わからない(笑)。でも、結論としてはこうしかなかったのかなっていう気はする。いろんな要素を省いたじゃないですか。
淡乃:そうですね、省きましたね。
幾原:だから、『春琴抄』のある程度のイメージを持ってきたら、 「え!?」ってなると思うんだよね。例えば、春琴は三味線弾いて琴弾くっていう風に思ってたら、全然三味線の音もこの音もしないんだよね(笑)。
淡乃:そうなんですよね(笑)。
幾原:僕たちはやめたわけじゃないですか。でも、結果それで良かったと思うんですよ。
淡乃:そうですね。それがないことで、普通とは違う部分にフォーカスされてます。だから体験と音のためにあらゆることを削ぎ落として洗練する方向にしてきましたね。
幾原:感情を観客が体験するっていうことに集中してる。感情だけは、とにかく音で追いかけるっていうこと。
淡乃:台本を作る段階から言ってましたよね。感情ごとに章を分けていくのはどうだとか。