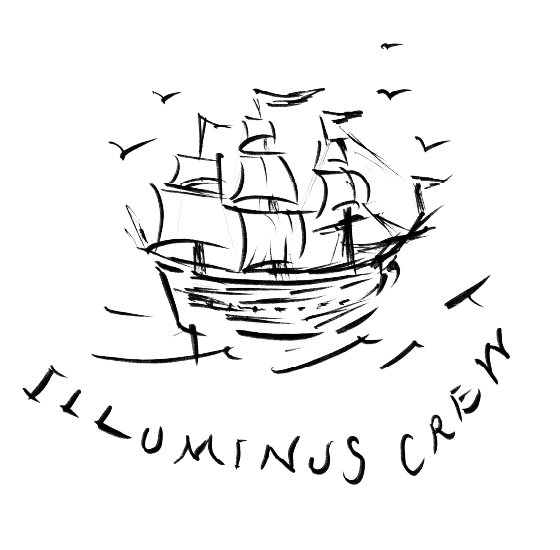25.10.1幾原邦彦×淡乃晶 対談 『春琴の佐助』が生まれた舞台裏
幾原:物語を伝えようとしたら多分ダメだと思ってたんですよね。物語を伝えようとして、細かいその感情のあやみたいなものを表現しようとした途端に退屈なものになるだろうと思ったんだよね。あと、観客がどういうことだろうっていう風に考えてしまう瞬間を作るのは良くないと思った。とにかく、ジェットコースターに乗ったら、もうすごいスピードで最後まで行ってしまう、みたいなのが良いと思ってて。で、そのためには、いかに観客に考えさせないかっていうことが大事なのかなとは思った。
淡乃:そうですね。だからこその削ぎ落としであったり、聴覚で振り切ることだったり。結果的にあまり見たことがないような形になってるので、朗読として普段想像するようなものとは多分、体験も感覚も違うものになるのではないかなとは思います。
幾原:観客がね、不安になるような瞬間が多分あると思うんだよね。そこがこの舞台の面白いとこだと思うんだよね。見てて不安になるっていうのが、いいところ(笑)。
淡乃:はい。本当にその、ギリギリですよね(笑)。
幾原:朗読劇と言いつつも、演劇なんで。舞台、ステージのものとして、成立するのかどうか、壊れるぐらいのさ、極まで行く瞬間っていうのを用意してるわけじゃないですか。ここがまさに体験してるっていうことでさ。今何が起こってるんだろうってなる朗読劇ってあんまないと思うよ。聞いてて不安になるって(笑)。
淡乃:(笑)。不安は言い換えたら、ドキドキするとか、ワクワクしたりする。
幾原 :どこに連れていかれるんだろうっていうね。そういうことだよね。だから、聞いててね、「自分たちが思っているその劇ではない」ってさ、「これ、どこに行くんですか」みたいなね。
淡乃:お話はもちろん、『春琴抄』に則ってはいるんですけど。でもやっぱり、それをこの新しい体験スタイルで、ステージで表現するのは、幾原さんが言ったように演劇でもあり、朗読でもあり、名前がまだつけられてないようなジャンルですね。まさに「Reading in the dark」、暗闇に導かれるみたいな、行為として独自のものを持ってるなとは思います。『春琴抄』という題材を今やることについてはどう考えてます?
幾原:谷崎潤一郎とか春琴抄は、もう何度も映画化されたり舞台化されたりしてるわけだけど、この作品自体が発表されたのはもう100年ぐらい前で。昔の作品なのにこれだけ胸を打つ話として通用するっていうのは、ある種類の、人の感情の本質的な部分を描いているからだと思うし。それが時代が変わっても古びないってところがすごいよなとは思うね。ちなみに僕はこれ、やっぱり全然いい話とは思わないんだよね。これは実はある種類のエゴだよね。春琴のエゴ。春琴はスーパースターなわけじゃないですか。スターとしてスタートして、そう振る舞っていてすごくプライドが高く、高貴なわけだよね。これはもう言ってしまえば、ロックスターとか映画スターみたいなものですよ。春琴は絶対に佐助をある一定の距離から中に入れないじゃないですか。原作にいろんなディティールがあって、今回僕らは省いてる部分もあるんだけど、ただそれにしたって、春琴は自分の心の中に佐助を基本的には近づけない。でもそれはスターが、タレントがファンを絶対に、どんなに慣れ合っても絶対にある一定の距離に近づけないっていう行為に近いと思うんだよね。
淡乃:現代のアイドルと応援してる人、推している人とか、そういう…。
幾原:そういうものに近いと思う。ところが春琴がその顔に火傷を負ってしまった瞬間、 弱くなるじゃないですか。そこで初めて、それまでの関係が、こう、揺らぐっていうのかな。 春琴はやはり、佐助が自分から離れていくんじゃないのかっていうことを恐れるわけじゃないですか。 それまで圧倒的なその立ち位置だったんですよ。関係性としては圧倒的に春琴が上だったんですよ。でもそこで初めて弱くなって、佐助が自分の前から去るっていうことを思って、弱い部分を見せていくわけだよね。 で、佐助がその弱さに入って、男女の距離を詰めることはしないじゃないですか。
淡乃:そうですね。しない。あくまでそのまま。
幾原:あくまでも私は、お師匠様の、春琴様のファンですっていうことで、その距離を維持するために、佐助はその行為(針で自分の目をつく)をするわけじゃない。ある意味、言い方を変えるとね、あるSMプレイをやっていて、 ちょっと目が覚める瞬間があるわけですよね。でもあえて元の関係に戻ろうとする。それが佐助にとっての愛の表現であるっていうさ。
淡乃: 絶対に春琴を普通の女性にしないみたいな。
幾原:そう、そこで春琴をスターのままにしておくっていうさ。そこがすごい。実際の人間関係だったら、なかなかこうはいかないと思うんだよね。心の隙に入っていって、距離を詰めるみたいなことをするっていうのが普通の人だと思うんだよ。それをしないっていうのは、もう凄まじい。なんていうのかな、春琴のことが好きなわけだよね。本当に。春琴をそのままにしておいてあげたいっていう。1周回ってすごい愛なわけだよね。
淡乃: 春琴も佐助もエゴイスティックなものをもっているけど、お互いのエゴが結局成就しているというか、エゴが寄り添い合っているみたいな。

幾原:だから、これはいい話なんかじゃなくて、残酷な話なんだよね。この残酷さやエゴみたいなものが愛に見えるところが、みんながこの『春琴抄』に惹かれるところだと思うんだよ。エゴをここまで突き詰めてそれでも人に求められるっていうのは、もう夢だよね。ある意味、表現者とかアーティストの夢だと思う。これはひとつのロマンチックな夢なわけだよね。こんな話あるわけないよっていうのが普通で、実際ないと思うんですよね。その気持ちを読者に「わかる」と思わせてしまうところが、この話のすごいところだよね。いい話じゃないんだけど、この話好きって言わせてしまう。ファンの前で勇ましいことばかり言うロックミュージシャンみたいな人の話で、そんな人がある日突然弱くなってしまった時にファンはどうするのかっていうさ。
淡乃:ついてこいって言ってくれたのに、その人がしばらく休みますって言った時ファンはどうするか、みたいな。そのスターがダメになってしまった時に、ファンはどうするのかという。
幾原:どっちにしてもスターにとっての夢でもあるしファンにとっての夢でもあるよね。普通は離れていくか、忘れていくか、その隙をついて距離を詰めるかのどれかなんだよ。でも佐助はそのどれでもない選択をするわけで。
淡乃:さっき幾原さんが言った「好き」ってのは、本当に汚れないというか。最初に感じた初期衝動のまま最後までそばにいるっていう形ですよね。その強烈な純粋さには惹きつけられるものがあります、自分も。この公演を見たお客さんがどう思うか…。
幾原:どうなんだろうね。ただ、相手の尊さとか、好きな部分を認めてあげたいとか、好きであるっていう気持ちみたいなね、そういうことを感じながら恋愛するっていうのは、普通にあることだと思うんで。そのままの形でいさせてあげたいっていうのは、ある意味ロマンチックな行為だとは思うね。 そこに関しては案外多くの人が自己投影できるような気はするけどね。ただ今話してきたようなことはあくまでも理屈でさ、その理屈を台本として何か構成するみたいなことになると、 ちょっと意識の高いものになっちゃって観客に考えさせちゃう瞬間ができちゃうんで、いかにあくまでも体験に持っていくかっていうね。
淡乃:はい。脚本作りをする中で大事にしてましたね、体験。
幾原:そこは淡乃さんの感性と僕の趣味があったとこだと思うんだよね。 壊れそうになる瞬間っていうのはさ、僕も好きなんだけど、淡乃さんが今回そこをずっと攻めてくるとは僕は思ってなかったんで。
淡乃: それはよかったです(笑)。
幾原:僕の方もさ、突っ込んでいったらさ、最後、僕もこう、壊れそうになるような方向に持っていこうとするから(笑)。そこも面白かったとこではあるよね。
淡乃:そうですね。2人揃って壊れそうになるところになんか集中しちゃって(笑)。お話が壊れるか壊れないかみたいなラインのせめぎ合いは、自分も幾原さんの作品を見てきて影響を受けてきた部分でもありますし、何より作品を見た時、驚きたいとかワクワクしたいとか、新しいものを見たいっていう気持ちが自分は強くて。今回、その幾原さんと朗読を一緒に作るにあたって、 こう攻めてきてもらえるというか、こういう方がいいんじゃないかってアイデアを出してもらえて刺激的ですし。なんか、この作品はただ見たことがないだけのものじゃないと思うんですよね。体感が違うというか。
幾原:これまでの仕事の中でも、これはかなり変わってる方なの?
淡乃:変わってますね。そもそも僕は、百合作品という、女の子同士の感情や関係性をずっと描いてきて。そもそも男性が演じられることや、男女の話であるっていうことが珍しいのもありますし。あと字面で綺麗な言葉を並べたがる癖が僕にはあって。いわゆるポエムのような言葉の良さを突き詰めて表現に落とし込みたいと思ってることが多いんですが、幾原さんと作っていると、文字の中に結構収まりがちだってことに気づかされるというか。