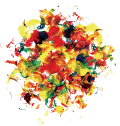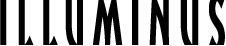『全便欠航』
僕たちはどこへも行けない。2020年、羽田空港国際線の出発ロビー。電光掲示板には美しいまでに同じ文字が並んでいた。全便欠航。
空港内には航空会社のスタッフしかおらず搭乗客は一人もいない。この国に誰も入ってこれないし、出ていくこともできない。天井が高く広大な空港ロビーには静寂が漂っていた。吸い込んではいけないはずの空気さえ清らかに感じる。
黄色の「距離を保とう」という看板が乱立している。すべてのレストラン、お土産物屋のシャッターは閉まっていてゴーストタウンのようだ。駐車場には車は一台も停まっていない。

尋常ではないことが起こっている。
そして緊急事態宣言。
街から人は消えた。

多くのビジネスが打撃を受けた。特に集客をして「ライブ」を見せるエンターテイメントには辛い時代へと突入した。音楽、演劇、映画、クラブ、スポーツ…。もちろん写真展さえも中止に追い込まれた。そして多くのエンターテイナーも家に閉じこもって何もできない状態だった。
どの業界も何をしたらよいかまったくわからず、まるで暗闇を這うように探りながらの前進、後退を繰り返していた。前進したつもりが前に現れたのがは崖っぷちだったり。
演劇業界もしかり。マスク、フェイスシールド、アルコール消毒、ビニールシート、間を空けての座席指定、観客数を半分に…。それでもだめなら無観客公演、配信公演。見えない敵に向かってあらゆる施策を施した。しかしどれほど努力してもそれが正しいのかどうかも誰にもわからなかった。
『タイムマシン』
そんな中、僕の著書『NO TRAVEL, NO LIFE』と『GIFT from Cuba』を原作とした舞台『PLAY JOURNEY!/アジア編・キューバ編』公演の話をいただいた。僕が昔放浪していたときのエピソードを舞台化した作品だ。主役はダブルキャストで、田中翔君と鵜飼主水君。この二人が若い頃の須田誠を演じてくれることになった。
僕のことを俳優さんが演じてくれる。僕の目の前に若い頃の僕が実体として存在する。映像や漫画ではなくもう一人の僕が時代を遡ってそこにいるのだ。これほど僕にとって痛快なことがあるだろうか。まるでタイムマシンだ。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』をリアルに体験している気分だ。
しかし原作が舞台化となるのは嬉しい反面、この時期での公演は神妙な気持ちではあった。なぜならば、多くの他の舞台で出演者の体調不良による公演中止が重なっていたからだ。あそこも中止、ここも中止…次はどこだ。まるで恐怖映画を見ているかのようでもあった。

『言葉のない世界』
緊張の日々が世界を取り巻く中、「須田誠が主演俳優のスダマコトを撮る」という企画が持ち上がった。それは面白いと直感した。2020年の僕が1994年の僕を撮影するのだ。タイムマシンから降りてきた過去のスダマコトを撮るなんて、こんな画期的な楽しい企画が他にあるだろうか。話を聞いた瞬間、やる!と思った。
ただ、同時に少々気がかりなこともあった。
僕は人物を「寄って撮る」というスタイルを信条としている。どれぐらい寄るかといえば、被写体に25センチまで寄って撮るのだ。すると写真に迫力が出て熱のある写真になる。
しかし世の中は、不要不急の外出自粛。ソーシャルディスタンス。外へ出て人に近づいてはいけないというお達しが出ている。
被写体と近距離で向き合う写真撮影は、時代の逆を行く撮り方だ。その得意な撮影方法は現在は封印せよといわれたようなものだ。
そこで提案をした。
「今の時代を残しましょう。2020年という時代に合わせて撮りましょう。僕の撮影方法が封印されたその時代を」
出した条件はこうだ。
・俳優さんに近づいてはいけない
・被写体までの距離は必ず2m以上離れる。
・集合してから撮影終了まで誰とも一切会話をしてはいけない
・指示は目と手振りだけ
あるのは被写体と僕の間にある信頼と見えないバイブレーションだけ。
しかし、俳優さんも、主催者もぜひチャレンジしてみようと理解を示してくれた。この限られた条件下。今までトライしたことのない撮影方法。きっと新しいものが生まれるはずだ。もとよりそれが芸術というものであったのではないか。

当日集合場所に俳優さん、スタッフが集まるが、みな離れた位置で、マスクで顔を隠し、目だけがその時の緊張感を醸し出している。声を出しての挨拶もせず無言で立っている。
当たり前のことかもしれないが改めて気がついたことがある。人は目と口を使い表情を加えてコミュニケーションをとっていたのだということ。髪の毛や、鼻や耳や、首筋では会話ができないのだ。
目と口と表情。今回はその重要な機能のうちの口と表情が封じられた。
人と人が顔を合わせているのだからみな何かを言いたい。無言の中もやもやとしたみんなの気持ちが伝わってくる。「こんにちは」、「今日はよろしくお願いします」、「今日のスケジュールは」など段取りさえ確認ができない。会話をしてはいけないというルールなのだから。
軽く頭を下げ上目づかいで「今日はよろしくお願いします」と目だけで伝える。かつて体験したことのない異様な風景だ。

僕は手を翻し「では撮影を始めましょう」と行動をうながす。あとは目と指と体の動きだけで撮影の指示を出す。無言の二人の静かな撮影が続く。スタッフは遠く離れた場所にいる。広い空港にもほぼ人がいない。
とても静かだ。
まるで真空の中で撮影をしているかのようだ。



最初はお互いに迷いがありすれ違いもあった。しかし段々と言葉がなくても、いや言葉がない分お互いを理解しようとする気持ちが強くなっていくのが手に取るようにわかる。
徐々にそれが快感にもなっていく。こうきたからこう。そこに立ったらこう。こっちではこう。なぜ僕の気持ちがわかるのか。次に出すアクションがわかるのか。言葉がないということは何メートル離れていても同じこと。僕の指示が遠くにいる被写体に届く。それは不思議な体験でもあった。






『本来の意味でのコミュニケーションとは』
あっというまに撮影時間は終了を迎える。この数時間、すべてが上手くいっていた。カメラと被写体と僕とバイブレーションが一体になりとても幸せな時間を過ごすことができた。ピントがどうのとか、露出がどうのとかテクニカルなことはどうでもよかった。もっと人間が持つ根源的な部分での幸福感があった。
結果は、同行取材してくださった佐野木雄太氏が当時書いてくれた文章が本質をついているので引用させてもらう。
「思えば、関係を築くとはそういうことではなかったか。声を発する、相手に触れる、それは確かに大切なことではあるが、それだけで関係を築くこともまた難しい。相手を知り、理解して、お互いのことを分かり合うことで初めて築かれる関係性。そこに必要なのは声や接触といった表面的なことではなく、本来の意味での『会話』や『ふれあい』なのではないか。すでに知り合っている人の新たな一面を発見する楽しみも、ぎこちないところから徐々に打ち解け通じ合う嬉しさも、無言のコミュニケーションの中でさえ生み出すことができる。須田氏の新しい挑戦は、それを証明していたように思う」
撮影が終わり、俳優さんにお疲れ様の一言もなく、握手もなく、2m離れた位置からただ無言で頭を下げ、別々の電車に乗り、音もなく静かに解散した。
タイムマシンから降りてきた自分自身を、言葉の無い静寂な空間で撮影をした。それはとても貴重で不思議な時間だった。それが2020年という年。

文・写真 須田誠
つづく…。
次回は2023年、舞台『NO TRAVEL, NO LIFE』の主演俳優、渡辺和貴君との出会いへ。